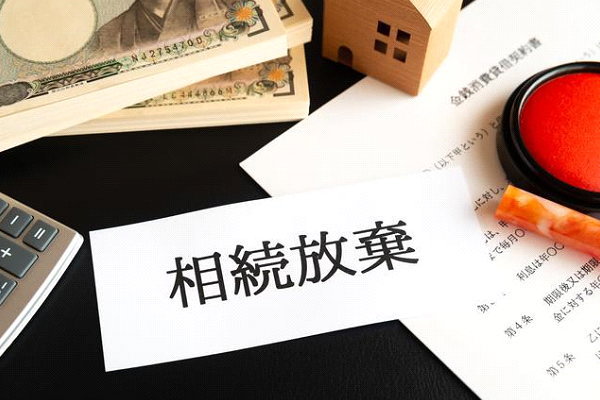
相続放棄を希望する場合は、法律で決められた期間内に管轄の家庭裁判所で手続きしなければなりません。期限内に手続きできるように、あらかじめ必要書類を確認し、準備しておきましょう。期限内に手続きしない場合は、原則として単純相続(正の財産と負の財産すべてを相続する)を承認したものとみなされます。
そのため、相続したくない事情や財産がある人は注意が必要です。この記事では、相続放棄を申し出る際の必要書類を被相続人との関係別に解説します。必要書類の入手方法などについても解説するので参考にしてください。
この記事で分かること
- 相続放棄とはどのような手続きか
- 相続放棄の必要な書類と提出方法
- 相続放棄の期限について
【あわせて読みたい】
▶︎マンションを相続して売却する際の流れは?税金や特例、確定申告について解説
もくじ
相続放棄とはどのような手続きか?
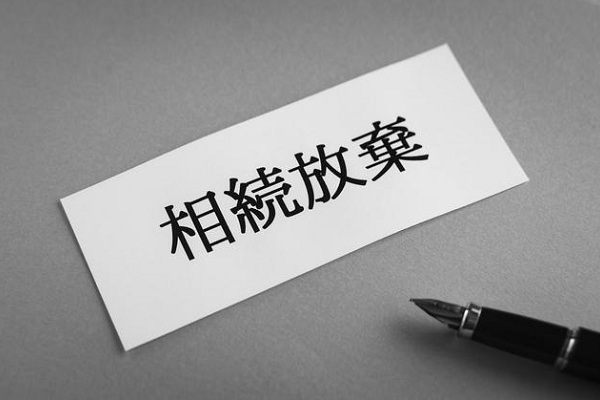
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しないことを自分の意思で決めた上で、法的に必要な手続きを行うことです。相続は、被相続人(故人)の財産および権利・義務を受け継ぐことですが、相続自体は権利で、義務ではないため相続するかしないかは相続人の自由意思で決められます。
なぜなら、相続対象となる財産および権利・義務には、預貯金や不動産など正(プラス)の財産だけでなく、借金や債務保証など負(マイナス)の財産も含まれ、場合によっては相続人が被相続人の負債を引き継ぐことになるからです。
相続放棄は、「正の財産も負の財産も一切受け継がない」ということを意味します。手続きとして、必要書類をそろえて管轄の家庭裁判所への提出することが必要です。原則、相続放棄を申し立てる本人が行いますが、放棄する人が未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が代理で行います。
相続放棄は、個々人に与えられた権利のため、法定相続人が複数人いる場合でも各相続人が放棄するかしないかを決めることが可能です。例えば、法定相続人が配偶者と長男、次男の3人で長男だけが相続放棄し、配偶者と次男は相続するということもできます。
なお、相続放棄は原則「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に行うことが必要です。期限内に手続きしないと単純承認したことになり、正と負のすべての財産や権利・義務を相続したことになるため、注意しましょう。
相続放棄の必要書類の提出先

相続放棄は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」で手続きをします。管轄となる家庭裁判所がわからない場合は、最高裁判所のホームページ(※)から調べることが可能です。
このときに提出する必要書類は、相続放棄をする人と被相続人の関係によって変わります。関係とは、配偶者や子、親などといった被相続人との間柄を指します。
不動産相続における放棄以外の選択肢

正の財産しかない場合であっても「不動産は相続したくない」という人が増加傾向にあります。主に「不動産を使わない」「維持費にお金がかかる」「相続税の負担が大きい」などが理由のようですが、一部の不動産だけを相続しないという選択はできません。
前述したように、相続放棄は「被相続人の財産を一切受け継がない」ということです。そのため、仮に相続財産として不動産以外に預貯金や株式などがある場合、不動産だけでなく預貯金や株式なども放棄しなければならなくなります。
そのため、相続財産の中に不動産が含まれている場合は、安易に相続放棄を決める前に、不動産の取り扱いについて別の方法を検討することが重要です。
方法としては、大きく以下の2つがあります。
売却(仲介だけでなく買取での売却も)
一つ目は、いったん相続した不動産を売却する方法です。相続手続き、売却手続きとステップを踏む必要がありますが、他の相続財産まで放棄する必要がなくなります。また、相続した不動産を売却することで売却代金を取得できるため、それを相続税の支払いに充てるという選択も可能です。
なお、相続税の申告・納税は「被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内」が期限となるため、売却代金で納税しようと考える人は注意してください。相続から売却までのすべてのステップでスムーズに手続きできるように、相続発生前から他の相続人とも話し合い、相続不動産売却の取り扱いが豊富な不動産会社を探して相談しておくのもおすすめです。
また、不動産会社に売却の仲介を依頼するだけでなく、不動産会社による買取依頼という選択肢もあります。相続不動産の売却に関しては、以下の記事で実際の経験者の声を参考にしてみると良いでしょう。
【あわせて読みたい】
▶︎相続不動産の売却に関する意識調査レポート:「会社・担当者への信頼」「地元の詳しさ」が売却仲介のポイント
相続土地国庫帰属制度
二つ目は「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法です。本制度は、所有者不明土地の発生を防止することを目的に2023年4月に始まった、相続した土地を一定の条件のもと国に引き取ってもらう制度です。
ただし、次の10の要件に当てはまる土地は引き取ってもらうことができません。
まず、以下の5つの却下事由に当てはまると申請自体することができません。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 現在他人が使用し、今後も使用が予定されている土地(通路、墓地、境内など)
- 土壌汚染されている土地
- 境界が不明の土地・争いがある土地
次に、申請は受け付けられても、以下の5つの事由に該当すると不承認となります。
- 崖(勾配30度以上かつ高さ5m以上)があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 地上に通常の処分・管理を阻害する有体物(工作物、放置車両など)がある土地
- 地下に除去が除去が必要な有体物(産業廃棄物、ガラ、浄化槽、井戸など)がある土地
- 袋地など、隣地との訴訟によらなければ解決できない土地
- その他、通常の管理や処分にあたって過分な費用・労力がかかる土地
事前に、帰属の条件にあてはまるかどうかを確認し、問題があれば早期に解決しておくことが大切です。
また、申請時には審査手数料、また承認された場合も10年分の土地管理費用相当額がかかります。
以下の記事で「相続土地国庫帰属制度」について詳しく説明していますので、参考にしてください。
【あわせて読みたい】
▶︎放棄に代わる新たな選択肢に?相続土地国庫帰属制度について弁護士が解説
相続放棄の手続きに必要な書類

ここからは、相続放棄を申し立てる際に必要となる書類を確認していきましょう。必要書類には、誰が相続放棄する場合でも共通して必要となる書類もありますが、被相続人との関係を証明するために個別に必要となる書類もあります。
それぞれの場合で必要書類を説明しますので確認してください。
すべてに共通する必要書類
すべての人に共通して必要となる書類には、以下のものがあります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)
- 連絡用の郵便切手(手続き先の家庭裁判所によっては不要な場合あり)
「相続放棄の申述書」は、裁判所所定の様式があり、どこの家庭裁判所でも取得できます。また、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。様式は、申述人が成年の場合と未成年の場合で異なるため、注意しましょう。
なお、同じ被相続人に対して複数の人が相続放棄をする場合、共通書類は1通のみで構いません。例えば、上記した「被相続人の住民票除票または戸籍附票」や、以下で紹介する各人の必要書類の中の同じ書類は、先に手続きする人が提出すればあとに手続きする人は提出不要です。
配偶者の場合
被相続人の配偶者が相続放棄をする場合は、「共通分」に加えて以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
なお、「共通分」として提出する配偶者の戸籍謄本の中には被相続人の記載もあります。自分の戸籍を取得するのが被相続人の死亡届が受理・反映されたあとであれば、死亡の記載もされているため、別途取得する必要はありません。
ただし、死亡届を出しても即日戸籍に反映されるわけではないので注意が必要です。
子の場合
被相続人の子が相続放棄をする場合も、「共通分」に加えて以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
子が未成年の場合など、被相続人と同じ戸籍に入っていれば、配偶者の場合と同様に自分の戸籍謄本の中に被相続人の記載もあります。その戸籍で被相続人の死亡の記載がされていれば別途取得する必要はありません。
なお、子が未成年である場合には特別代理人が必要になります。その場合、親(被相続人の配偶者)は特別代理人になることができないため、利益相反関係にない人物を特別代理人とする必要があります。
その際には、以下のような書類も追加で必要になります。
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
- 利益相反に関する資料
孫の場合
被相続人の子がすでに死亡して、その人に子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が代襲相続人となります。代襲者である孫が相続を放棄する場合は、被代襲者(被相続人の子=自分の親)が死亡していることを証明する書類が必要です。
「共通分」に加えて以下の書類を提出しましょう。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
被代襲者と相続放棄をする本人が同じ戸籍に入っていれば、別途取得する必要はありません。
親の場合
被相続人の親が法定相続人となる場合で、相続放棄をしたい場合は「共通分」に加えて以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
親が法定相続人となるのは、「被相続人(自分の子)に配偶者がいない」「配偶者はいても子ども(または孫、ひ孫など)がいない」といった場合です。被相続人の結婚歴や、子の出生・死亡歴の有無を確認するための書類として、出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹が法定相続人となるのは、「被相続人に配偶者がいない」「配偶者はいても子ども(または孫、ひ孫など)および親(または祖父母)がいない」といった場合です。これらを確認するための書類として以下の書類が必要です。
兄弟姉妹が相続放棄をしたい場合は、「共通分」と合わせて提出しましょう。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属(親および祖父母など)の死亡の記載のある戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
甥姪の場合
本来、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるところ、その人がすでに死亡している場合は、その人の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。代襲者の甥・姪が相続放棄をする場合は、被代襲者(被相続人の兄弟姉妹=自分の親)が死亡していることを証明する書類が必要です。
「共通分」に加えて以下の書類を提出しましょう。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属(親および祖父母など)の死亡の記載のある戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
- 被代襲者(本来の相続人=自分の親)の死亡の記載のある戸籍(除籍や改製原戸籍)謄本
相続放棄の必要書類の提出方法

相続放棄の必要書類を提出する方法には、「窓口への持参」と「郵送」の2つがあります。どちらも提出先は「被相続人が最後に居住していた地域を管轄する家庭裁判所」です。裁判所の種類には、地方裁判所や簡易裁判所などもあるため、間違わないようにしましょう。窓口への持参は、提出書類に不備がないか、その場でチェックしてくれるため安心です。受付時間を確認してから行きましょう。
郵送は、遠方に住んでいる場合や日中に出向くのが難しい場合でも手続きできるため、安心です。書類の不足、記入もれや押印もれなどの不備がないか確認してから送りましょう。
相続放棄の必要書類の受け取りにかかる期間

「相続放棄の申述書」は、裁判所のホームページからダウンロードできます。また、裁判所の窓口に行けばすぐにもらえるため、戸籍謄本など他の書類を一式そろえて持参し、その場で申述書に記入することもいいでしょう。その他の住民票除票や戸籍謄本などは、市区町村役場の窓口に行けば即日交付してもらえます。
交付してもらうためには、窓口に行く人の本人確認書類が必要になるため、忘れずに持参しましょう。また、住民票除票や戸籍謄本などは郵送で取得することも可能です。その場合、発行手数料の定額小為替または現金書留を合わせて送らなければなりません。定額小為替は、郵便局またはゆうちょ銀行でのみ取り扱っており、まずはその手配が必要です。
すべてをそろえて郵送してから受け取るまでにかかる期間は、郵便事情にもよりますが、10~14日間が目安となります。時間はかかりますが、「遠方に住んでいる」「日中に出向くのが難しい」「転居が多くて複数の市区町村役場に行く必要がある」といった場合は、郵送をうまく活用するとよいでしょう。
相続放棄の必要書類の取得費用

住民票の除票や戸籍謄本などを発行する際は、手数料がかかります。市区町村によって金額が異なる場合もありますが、一般的な目安額はそれぞれに以下のとおりです。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:1通300円
- 申述人(相続放棄する本人)の戸籍謄本:1通450円
- 死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本:1通750円
【郵送の場合】
・定額小為替発行手数料:1枚につき200円
窓口で取得する場合、キャッシュレス決済に対応している市区町村役場もあるため、事前に用意した金額が不足していている場合などでも安心です。しかし、郵送の場合は定額小為替または現金書留の金額に過不足があると、正確な金額のものを再送するまで手続きしてもらえません。
「多めに払っておけば大丈夫」というものではないため、事前に管轄の市区町村役場のホームページなどで確認しておきましょう。なお、郵送での取得の際に必要となる定額小為替には、1枚あたり200円の手数料がかかります。
相続放棄の期限について

相続放棄ができる期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」です。期限内に手続きしないと単純承認したことになり、正と負のすべての財産や権利・義務を相続したことになるため、注意しましょう。
しかし、場合によっては例外もあります。そこでここでは、3ヵ月以内であっても相続放棄ができない場合や、3ヵ月を過ぎても手続きできる場合について確認しておきましょう。
期限前でも相続放棄できない場合
まず、被相続人が生存している間は相続放棄できません。なぜなら、生存中はまだ「相続の開始」の状態にはなっていないからです。相続の開始とは、相続対象となる人が死亡したときで、それによってその人は被相続人となります。仮に自分が相続人となることがわかっている場合でも、あくまで「自己のために相続が開始(被相続人が死亡)したときから3ヵ月以内」に手続きをすることが必要です。
一方、相続発生後かつ3ヵ月以内であっても、相続を承認したあとには相続放棄ができません。例えば被相続人の財産に手を付けてしまうと単純承認したとみなされる可能性があるため、注意が必要です。
原則、被相続人の財産の使用や処分ができるようになるのは、すべての相続手続きが終わったあととされています。例えば、以下のような行為をすると相続したものとみなされ、相続放棄できない可能性があるため、押さえておきましょう。
- 被相続人名義の預貯金を払い出した
- 被相続人あてに届いていた請求書の支払いを被相続人の財産から支払った
- 被相続人の家財や所有物を自分のものにした
- 被相続人の家財や所有物を第三者にあげた
- 被相続人の家財や所有物を捨てた など
他にもさまざまなケースが考えられますが、深く考えずに行った行為によって相続放棄ができなくなってしまう可能性もあることを理解しておきましょう。
相続放棄の期限を延ばす方法
一般的に、被相続人の財産状況がわからなければ、相続放棄するかどうかの判断はできません。しかし、実際の相続では正の財産、負の財産を含めて被相続人の財産に何がどれだけあるかわからなかったり、相続財産の調査に時間がかかったりして3ヵ月以内に相続放棄の判断や手続きができない可能性もあります。
その場合は、家庭裁判所に申請することで相続放棄の期間を延ばしてもらうことが可能です。3ヵ月の期限内に相続放棄を決められない人は、本来の期限となる3ヵ月以内に申請をしましょう。ただし、期間の伸長(延ばすこと)が認められるためには、「財産調査などに時間がほしい」など合理的な理由が必要です。
なお、3ヵ月が経過し単純承認したあとになっても相続放棄ができる可能性もあります。例えば、相続財産がまったくないと信じていたにもかかわらず、あとになって相続財産があることを知ったような場合です。この場合は「そのように信じたことに相当な理由」があれば、「相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3ヵ月以内」に家庭裁判所へ申し立てることで相続放棄が認められることがあります。
不動産については売却の可能性も検討しよう

相続放棄は、正の相続財産よりも借金など負の財産のほうが大きい場合に行うのが一般的です。しかし、近年は正の財産しかなくても「不動産を相続したくない」という理由で相続放棄を検討する人も増えているようです。特に、2024年4月から相続登記が義務付けられたこともあり、代々にわたって名義変更されていない不動産がある場合は、なおさらかもしれません。
相続放棄をする際の必要書類は、被相続人との関係が遠くなるほどより多くの書類を提出する必要があります。その場合、必要書類を取り寄せる手間がかかります。さらには、相続財産の種類ごとに放棄するかを選べるのではなく、すべての財産を放棄することになります。
これらの負担やメリット・デメリットを熟慮したうえで、放棄するかどうかを判断することが大切です。もし、「相続したくない不動産がある」という理由で相続放棄を検討している場合は、対象不動産を売却することも一つの方法です。いったん相続手続きを踏むステップはありますが、それによって不動産を手放し、他の財産を受け継ぐことが期待できます。
相続と売却手続きを並行して進めることも可能です。ただし、相続に関する煩雑な手続きや期限を考慮すると、相続不動産の売却に長けている不動産会社を選ぶのが賢明です。LIFULL HOME'Sなら全国4,500社以上(2024年10月時点)の不動産会社と提携しているため、地方に所在する相続不動産の売却でも経験のある不動産会社を見つけやすいでしょう。自分の必要性に合う、良い不動産会社選びにぜひご活用ください。
記事監修
橋本 秋人(はしもと あきと)
FPオフィス ノーサイド代表。CFP®、1級FP技能士、終活アドバイザー。 大学卒業後、住宅メーカーで30年以上相続対策、個人の不動産活用、CREなどを担当。独立後はセミナー講師、執筆、相談、実行支援を中心に活動。 終活アドバイザー協会(NPO法人ら・し・さ)副理事長。日本FP協会評議員
・FPオフィスノーサイド
・NPO法人 ら・し・さ

