
親などの親族が亡くなったことに伴い、土地を相続する場合があります。
その際、兄弟など相続人が複数いる場合は、どうやって土地や建物を分けるべきか悩んでしまうという人もいるでしょう。
- 土地や建物の相続手続きの流れを知りたい
- 土地や建物の遺産分割方法を理解したい
- 土地や建物の相続税を軽減する主な特例を知りたい
この記事では、上記のような悩みを抱える人向けに、土地の相続手続きの流れを詳しく解説します。
この記事で分かること
- 土地や建物における相続手続きの流れ
- 土地や建物の遺産分割方法
- 土地や建物の相続税を軽減する主な特例
- 相続した土地や建物を売却する手順
- 相続した土地や建物を売却する際の注意点
【あわせて読みたい】
▶︎土地売却の基礎知識まとめ|土地を売る方法や流れ・注意点を解説
もくじ
土地や建物における相続手続きの流れ

相続で土地や建物を取得する場合は、主に以下の手続きを行うことになります。
- 相続人・相続財産の調査
- 遺言書の有無を確認
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付
相続人・相続財産の調査
相続人と相続財産の調査は、親などの親族が亡くなったときに実施するものです。
一般的に法定相続人が誰なのか確認するために戸籍を調査します。また、相続財産を調査し、借金などのマイナス財産も含めたすべての遺産について調べます。
戸籍を見ただけでは分からないこともあるため、法定相続人の調査は専門知識を持つ司法書士に依頼するとよいでしょう。
また、不動産に関する相続財産を調査するときは、固定資産税課税明細書を確認します。被相続人あての納付書が見つかれば、不動産の所有状況を確認することができます。
遺言書の有無を確認
相続人・相続財産の調査が完了したら、遺言書の有無を確認します。自宅を探しても親の遺言書が見つからない場合、公正証書遺言が残されていないか確認します。 平成元年以降に作成された公正証書遺言は、全国の公証人が利用できる「遺言検索システム」などで調べることが可能です。戸籍謄本と本人確認書類を用意すれば、最寄りの公証役場で利用できます。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。
相続人全員が参加して協議し、結果を書類に残さなければなりません。相続人が1人でも欠けた状態で実施すると、無効になるため注意が必要です。
遺産分割の期限は法的に決められていませんが、相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に実施する必要があります。
相続税の申告・納付
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に実施します。
期限までに申告しない、あるいは実際に相続した財産額より少ない金額で申告すると、延滞税や加算税が追加される場合があるので注意しましょう。
なお、相続税は「現金一括」で納めるのが基本ですが、「延納(何年かに分けて納める)」と「物納(相続財産などで納める)」という制度もあります。延納・物納制度を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申出て許可を受けましょう。
【あわせて読みたい】
▶︎不動産は相続前に売るべき、それとも売らざるべきか?
土地や建物の遺産分割方法

不動産を相続した場合の遺産分割方法は、主に以下の4つがあります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割
現物分割とは、不動産や株式などの財産をそのまま相続する遺産分割方法です。
例えば、長男は「建物+土地付き」の実家、次男は現金などを受け継ぎます。不動産を現物分割で相続するケースとして、以下の例が挙げられます。
- 土地を分筆して分ける
- 建物を区分所有にして分ける
土地のみを相続する場合では、分筆して現物分割するケースが一般的です。 相続分に応じて分筆すれば、物理的に分けられるため単独で所有することが可能です。
投資用マンションなどを複数の相続人で受け継いだときは、建物を区分所有にして現物分割するケースもあります。例えば、1・2階部分を長男、3・4階部分を次男といった配分で分割し、自分が所有する部分を売却することもできます。
ただし、相続人全員が区分所有建物としての現物分割に同意しなければ実行できません。
代償分割
代償分割とは、1人または複数の相続人が財産を取得し他の相続人に代償金を支払って清算する遺産分割の方法です。現物分割が難しい場合に実行されます。
例えば、3,000万円の価値がある土地付き一戸建ての実家を兄弟2人で相続するケースで、兄がすべて取得し弟に相続分である1500万円を代償金として支払う方法です。
ただし、取得する人に代償金を支払えるだけの資力がなければできません。相手が合意すれば、現金ではなく土地や権利などでも可能です。
換価分割
換価分割とは、相続した不動産などを売却し売却金を法定相続人の間で分配する方法です。
例えば、2人の子どもが相続人で土地付き一戸建ての実家を3,000万円で売却した場合、1,500万円ずつ売却金を受取ります。
「現物分割」「代償分割」が難しい場合に利用される方法で、不動産では実家を受け継ぐ人がいない場合によく利用されます。
共有分割
共有分割とは、相続した不動産を法定相続人で共有して分割する方法です。
例として、実家を兄弟で1/2ずつ取得するケースが挙げられます。不動産に関する権利が等分のため、売却するときは共有者全員で合意しなければなりません。自分で自由に使用できる範囲も限られています。
また、将来的に共有物の相続人は増えていくため、権利関係が複雑になる恐れがあります。相続での分割方法としては、先々問題が発生するリスクのある方法と言えるでしょう。
【あわせて読みたい】
▶︎不動産相続の基礎知識。相続登記の手続きの仕方とは?
土地や建物の相続税を軽減する主な特例

被相続人が遺した土地や建物を相続する場合、相続税負担を軽減する特例があります。
- 小規模宅地等の特例
- 相続税の配偶者控除
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
例えば、相続した実家の評価額が1,000万円だった場合、この特例を利用することで、評価額を200万円にまで抑えることができる場合があるのです。この制度は、残された家族の相続税負担が大きくならないために作られました。
小規模宅地等の特例の対象となる土地は以下の3種類です。
- 特定居住用宅地(実際に住んでいた土地)
- 特定事業用宅地等(事業を行っていた土地)
- 貸付事業用宅地等(アパートなどを賃貸していた土地)
小規模宅地等の特例が適用される主な要件は以下のようになっています。
| 特例の種類 | 主な要件 |
|---|---|
| 特定居住用宅地(減額割合80%) |
・被相続人の配偶者が相続 ・被相続人と同居していた人(子どもなど)が相続 ・相続前の3年間、借家住まいの相続人が取得(被相続人に配偶者や同居人がいない場合) |
|
特定事業用宅地等(減額割合80%) ※貸付事業用以外 |
・相続税の申告期限まで土地を保有し、事業を継続 ・被相続人の事業に使用されていた土地 (不動産貸付業などは除く) |
| 貸付事業用宅地等(減額割合50% ※特定同族会社事業用宅地等は80%) |
・相続開始の直前において被相続人の事業(不動産貸付業、駐車場業など)で使用 ・被相続人の貸付事業(アパート経営など)を相続税の申告期限までに引き継ぎ、申告期限までその貸付事業を継続 |
※参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
小規模宅地の特例の適用要件や減額される割合は、土地の種類や利用状況、相続人に応じて異なり、それぞれ上記の要件を満たさなければなりません。
相続税の配偶者控除
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続した遺産額が、以下の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからない制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、相続人が配偶者と子ども1人のケースでは配偶者の法定相続分は全体の2分の1となります。したがって、遺産が1億円の場合で、5,000万円までの相続であれば、配偶者に税金はかかりません。
また、遺産が1億6,000万円以内であれば、すべての財産を配偶者が相続し、相続税額を0円にすることも可能です。ただし、二次相続で一度に子どもが相続すると、子どもには配偶者控除のような特例がないため、税負担が重くなる可能性もあります。
配偶者控除を利用するときは将来的な二次相続も考慮しておく必要があるでしょう。
相続した土地や建物を売却する手順
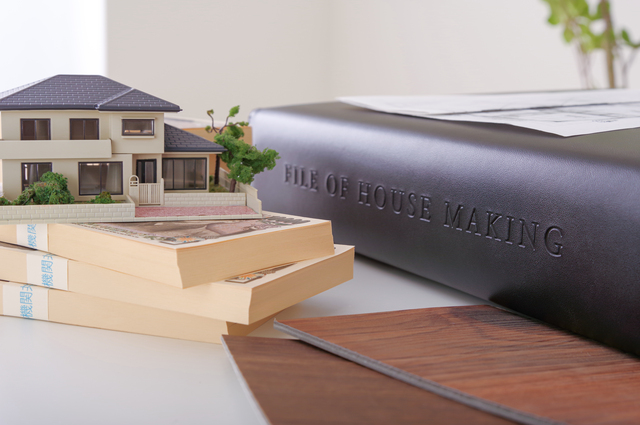
相続した不動産を売却する場合、一般的に以下の手順で進めることになります。
- 相続登記で名義変更する
- 不動産会社へ査定を依頼する
- 売買契約の締結・引渡し
ここでは、相続した土地や建物を売却する手順について解説します。
相続登記で名義変更する
相続した不動産を売却するには、相続登記が必要です。相続登記とは、所有者の名義を被相続人から相続人に変更する手続きを指します。
不動産に関する権利は民法により、登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できません。つまり、自分名義の場合のみ売却ができます。
そのため、相続人になったら速やかに相続登記することをおすすめします。自分でも登記できますが、内容が複雑なため司法書士など専門家に依頼すると良いでしょう。
相続登記は数週間から2ヶ月程度かかることもあるので、早めに名義変更しておかないと売り時を逃すことも考えられます。
なお、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。正当な理由がないのに申告しない場合は、10万円以下の過料が科される場合があるので注意が必要です。
※参考:法務省民事局
【あわせて読みたい】
▶︎名義変更とは? 家を売却するときに押さえておきたい登記手続き
不動産会社へ査定を依頼する
登記を完了して自分名義の不動産となったら、いよいよ売却活動を始めます。まずは、不動産会社へ査定を依頼しましょう。
複数の不動産会社が提示した査定価格を比較したり、会社の特徴を調べたりすることで、信頼できる不動産会社を見つけることができるでしょう。
複数社に査定依頼するときは、LIFULL HOME'Sの不動産一括査定がおすすめです。不動産会社の特色や意気込みが分かる情報も豊富に提供しているので、自分と相性の良い不動産会社を探せます。
売買契約の締結・引渡し
信頼できる不動産会社が見つかり媒介契約を締結した後、不動産会社の担当者が売却活動を始めます。希望に合った買主が現れたら売買契約を結び、手付金を受取ります。
多くの買主は売買契約成立後に金融機関で住宅ローンを申し込むため、買主が審査に通ってから残った代金を受取るのが一般的です。
原則、残代金の決済と引渡しは同時に行われることが多く、住宅ローンを利用する場合は銀行の一室で実行するのがほとんどです。司法書士も同席のもとで、所有権移転登記の手続きを実行します。
【あわせて読みたい】
▶︎土地の売買契約書は正しく把握しよう! 売買契約を結ぶ流れと注意すべきポイント
相続した土地や建物を売却する際の注意点

ここでは、相続した土地や建物を売却する際の注意について解説します。
- 主に3つの税金が発生する
- 土地を売却するタイミングは3年以内が望ましい
- 必ず相続登記しなければならない
主に3つの税金が発生する
相続した土地や建物を売却するときは、主に以下の3つの税金が発生します。
- 譲渡所得税(利益が発生した場合に課税)
- 印紙税(売買契約書に課される税金)
- 登録免許税(抵当権抹消のための登記費用)
相続した不動産を売却して利益が発生した場合に発生するのが譲渡所得税です。「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」などの特例を利用すると、所得税を抑えられます。
また、売買契約書は課税対象文書のため、印紙税も納付しなければなりません。売買契約書に取引金額に応じた収入印紙を貼付け、消印することで納付したとみなされます。
令和6年3月31日までに作成される売買契約書については、印紙税の軽減措置が適用されます。(1億円までは通常の半額が軽減)
親が住宅ローンを利用していた場合は、抵当権抹消のための登記が必要な場合があります。
ローンを完済していても、抵当権を抹消していないケースもあるので注意が必要です。抹消されていない場合は、抵当権抹消登記しなければなりません。
【あわせて読みたい】
▶︎土地売却にかかる費用(手数料)や税金はいくら?必要なコストを解説
▶︎土地売却にかかる税金とは? 使える5つの控除・特例も紹介
土地を売却するタイミングは3年以内が望ましい
誰も利用しないなどの理由で相続した土地を売る場合は、相続税の申告期限の翌日から3年 以内に売却すると譲渡所得税が軽減される特例があります。
これが「相続税の取得費加算」と呼ばれる制度です。特例の適用を受けるための要件は、主に以下の通りです。
- 相続や遺贈により財産を取得している
- その財産を取得した人に相続税が課税されている
- 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却
なお、「相続空き家の3,000万円特別控除」とは併用できません。
【あわせて読みたい】
▶︎土地売却した場合の節税方法をシミュレーション付きで解説
必ず相続登記しなければならない
不動産を売却するときは、自分名義でないと売却することはできません。
そのため、相続後すぐに売却するとしても、前提として被相続人から不動産を受け継ぐ人に名義変更します。
相続登記を済ませておかないと、所有者としての権利を主張できないので注意が必要です。 目安として、相続が発生してから1年以内に登記するのをおすすめします。
土地の相続に関するよくある質問
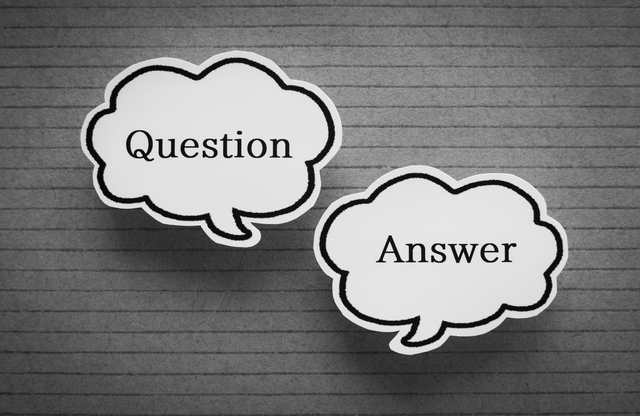
最後に、土地の相続に関するよくある質問を紹介します。
- 土地相続の優先順位と法定相続分は?
- 土地の相続税がかからないケースはある?
- 2,000万円の土地にかかる相続税はいくら?
土地相続の優先順位と法定相続分は?
土地だけに限りませんが、遺産を相続するには優先順位と法定相続分があります。法定相続分は、家族構成により違いがあります。
相続の優先順位と配偶者がいる場合の法定相続分は、以下の通りです。
| 相続人 | 優先順位 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 子ども(子どもが先に死亡して孫が生きている場合には孫などの直系卑属) | 第1順位 |
・配偶者1/2 ・子ども(全員分)1/2 |
| 親(親が先に死亡していれば祖父母などの直系尊属) | 第2順位 |
・配偶者2/3 ・親1/3 |
| 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していれば甥や姪) | 第3順位 |
・配偶者3/4 ・兄弟姉妹1/4 |
土地の相続税がかからないケースはある?
相続した土地を売却しても相続税がかからないケースは、以下のような場合が考えられます。
- 「正味の遺産総額≦基礎控除額」であれば申告不要
- 「配偶者の税額軽減の特例」など相続に関連する特例を利用して税額を0円にする
正味の遺産総額が各相続人の基礎控除額(相続税の非課税枠)以内なら、申告する必要がありません。基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円×法定相続人の人数)
また、配偶者の税額軽減の特例では、遺産総額が1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分相当額(正味の遺産総額の1/2)までのいずれか多い方の金額は税金がかかりません。
2,000万円の土地にかかる相続税はいくら?
相続財産が2,000万円の土地のみの場合には、原則、相続税は課税されません。
相続税には基礎控除があるため、相続する財産が3,600万円以内であれば相続税は0円となります。相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
土地の相続は計画的に実行しよう

相続財産を分割するときは、兄弟間などでトラブルになるケースも多く、上手に分割する必要があります。相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内のため、それまでに問題なく相続を完了するのが理想です。
土地を複数人で相続するときは分割方法についてよく話し合い、揉めることのないよう計画的に実行しましょう。
記事執筆・監修
矢口 美加子(やぐち みかこ)
宅地建物取引士、整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級の資格を保有。建築・不動産会社で事務をしながら、家族が所有する賃貸物件の契約や更新業務を担当。不動産ライターとしてハウスメーカー、不動産会社など一部上場企業の案件を中心に活動中。

