
不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税が発生します。不動産売却による利益が高額であれば譲渡所得税も高くなります。
こうした場合に、ふるさと納税を活用して、メリットを享受する方法があります。
この記事では、不動産売却において、ふるさと納税がメリットになる理由や、ふるさと納税の控除上限額についてシミュレーションを交えて解説します。
この記事で分かること
- 不動産売却後のふるさと納税がメリットとなる理由
- 不動産売却におけるふるさと納税の控除上限額
- 不動産売却後のふるさと納税の控除上限額をシミュレーション
- 不動産売却後にふるさと納税する流れ
- 不動産売却でふるさと納税する際の注意点
そもそもふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分の故郷や応援したい自治体などに自らの意思で寄付できる制度のことです。
ふるさと納税をした翌年に手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分の全額について所得税の還付や住民税の控除が受けられる嬉しい制度です。実質、自己負担額2,000円で応援したい地域の名産品などをもらうことができるため、近年利用者が増えています。
制度が開始される前までは、住民税は自分の住まいがある自治体に納める仕組みでした。しかし、ふるさと納税が施行されて以降は、寄付金の使い道や寄付先の自治体を選べるため、応援したい自治体の力になれます(※1)。
控除上限額は、収入や家族構成などにより異なります。収入と家族構成別の控除額の上限の目安については、総務省がまとめているので参考にしてください。
不動産売却時のふるさと納税がメリットになる理由
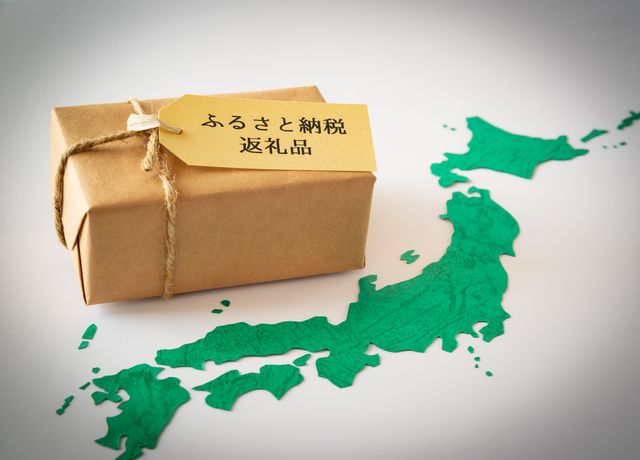
前述のとおり、ふるさと納税は、寄付金のうち2,000円を超える部分について所得税や住民税から全額控除される制度です。
不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税が課税されます。売却益が大きければ、その分、譲渡所得税も高額になる可能性がありますが、ふるさと納税によりメリットを受けられる場合もあります。
ここでは、不動産売却後にふるさと納税をすることでメリットを受けられる仕組みを解説します。
ふるさと納税によってメリットを得ることができる仕組み
不動産売却時にふるさと納税をすることでメリットを得ることができる仕組みは以下の通りです。
- 不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税が発生する
- 譲渡所得税額が高くなると、ふるさと納税の控除上限額が上がる
- ふるさと納税でもらえる返礼品が増える
- 所得税の還付・住民税の控除を受けることができ、結果的に2000円の負担で済む
譲渡所得が高額なほど控除上限額が上がるため、もらえる返礼品の数が多くなる点が大きなメリットです。ふるさと納税を実施しなければ、納税先の自治体の名産品などを得ることができず税金を納めるだけになるため、たったの2000円で返礼品の分だけ得することになります。
所得税の還付金が指定した口座に振り込まれるのは、確定申告をしてから1〜2ヶ月後です。
不動産売却におけるふるさと納税の控除上限額
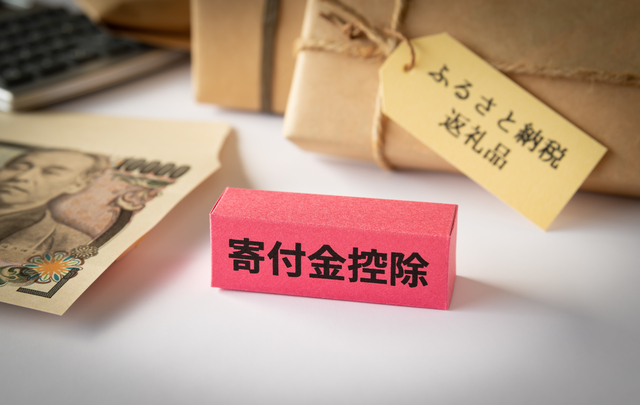
前述したように寄付した額が控除対象となる、ふるさと納税には控除上限額が設けられています。
ここでは、控除上限額や住民税所得割額の計算方法を解説します。
控除上限額の計算方法
ふるさと納税で控除できる、控除上限額の計算式は以下の通りです。
控除上限額= (個人住民税所得割額+譲渡所得税にかかる住民税)×20%÷{100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021)}+負担分2,000円
※参考1:ふるさと納税 控除の目安と限度額の計算方法|ふるさとぷらす
※参考2:ふるさと納税のしくみ|税金の控除について|総務省
住民税所得割額の計算方法
住民税は"均等割"と"所得割"という税金で成り立っています。所得割は前年の所得金額に応じて負担する税です。均等割とは異なり、所得金額を基に計算します。
所得割額の計算方法は、以下の通りです。
- STEP1.課税所得金額を計算
- STEP2.算出所得割額を計算
- STEP3.所得割額を計算
STEP1.課税所得金額を計算
その年に確定した収入金額や支払いを受けた収入金額の合計から、必要経費などを差し引いた金額を計算します。この金額が、課税総所得金額です。
課税所得金額=所得の合計額 - 所得控除の合計額
STEP2.算出所得割額を計算
次に、算出所得割額(※税額控除する前の所得割額)を計算します。
算出所得割額=課税所得金額×税率(10%)
STEP3.所得割額を計算
調整控除・税額控除を算出所得割額から差し引き、所得割額を計算します。
なお、調整控除とは、税負担が増えないように調整し個人住民税の所得割額から一定額を控除することを指します。
所得割額=算出所得割額-(調整控除+税額控除)
税額控除には、配当控除や住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除などが適用されます。
※参考1:均等割・所得割とは何ですか|新座市ホームページ
※参考2:住民税の計算方法|板橋区公式ホームページ
※参考3:(最初にお読みください)税額の計算方法|八王子市公式ホームページ
※参考4:調整控除とは?|日の出町ホームページ
不動産売却後のふるさと納税の控除上限額をシミュレーション

ここでは、ふるさと納税の控除上限額をシミュレーションとして、目安表にまとめました。
同じ収入でも、家族構成によって年間上限税額に違いがあります。おおよその目安として、以下の表を参考にしてください。
【全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安】 ※2,000円を除く(単位:円)
寄付する人の給与収入 |
ふるさと納税をした人の家族構成 | |||
|---|---|---|---|---|
| 独身または共働き | 夫婦のみ | 共働き+子1人 (大学生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | ー |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 12,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 28,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 43,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 66,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 85,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 138,000円 | 119,000円 |
| 1,000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 163,000円 | 144,000円 |
参考:全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安|総務省
上記から、年収が多くなるほど年間上限税額も増加することが分かります。
不動産売却後にふるさと納税する流れ

不動産売却後にふるさと納税する流れは以下の通りです。
- STEP.1不動産売却後に譲渡所得税を計算する
- STEP.2寄付先の自治体を選ぶ
- STEP.3寄付金を支払う
- STEP.4返礼品や寄付金受領証明書を受取る
- STEP.5確定申告を実施する
- STEP.6所得税の還付や住民税の控除を受ける
ここでは、上記6つのステップをそれぞれ解説します。
STEP1.不動産売却後に譲渡所得税を計算する
不動産を売却した際に利益が発生した場合は、譲渡所得税の納付義務が発生します。
譲渡所得税の税率は以下の通りです。所有期間5年をラインにして、税額が大幅に変わります。
| 短期譲渡所得の税率(所有期間5年以内) | 所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63% |
|---|---|
| 長期譲渡所得の税率(所有期間5年超) | 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315% |
所有期間は譲渡日が属する年の1月1日時点を基準として計算します。たとえば6月30日に売却した場合、6月30日時点ではなく、その年の1月1日時点で所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = ①譲渡収入ー(②取得費+③譲渡費用)
①…物件価格
②…物件購入価格+購入時の諸費用+購入後の設備工事・リフォーム費用−減価償却費
③…売却時にかかった諸費用
例えば、 物件売却価格が5,000万円、取得費が4,000万円、譲渡費用が250万円の場合は、上記の計算式に当てはめて譲渡所得を算出します。
譲渡所得 = 5,000万円– (4,000万円 + 250万円)=750万円
上記の結果から、譲渡所得は750万円となります。
なお、マイホームを売却した場合は、要件に該当していれば"居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例"が適用され、譲渡所得税が発生しないケースがあります。
STEP2.寄付先の自治体を選ぶ
譲渡所得税を算出したら、次は寄付先の自治体を選びます。近年では、ふるさと納税サイトが数多く提供されているので、インターネットでじっくり選ぶことがおすすめです。
名産品を楽しみたい人はご当地の"返礼品"から探すと良いでしょう。寄付金の使い道からも自治体を選ぶことができます。
STEP3.寄付金を支払う
寄付したい自治体が見つかったら、寄付者の氏名や連絡先、住民票の住所、返礼品の届け先を設定して寄付金を支払います。
寄付する際は、控除を受ける人の氏名を入力します。住民票の登録と異なる場合は、寄付金控除の対象とならないおそれがあるので注意しましょう。
ふるさと納税関連の書類は、自治体から住民票に登録がある住所に届きます。
寄付金の支払い方法にはクレジットカードや銀行振替、PayPayなどの電子マネーなど、さまざまな決済方法があります。
STEP4.返礼品や寄付金受領証明書を受取る
寄付金を支払った後、自治体から返礼品が届きます。確定申告に必要な寄付金受領証明書は、返礼品と別に寄付先の自治体から寄付者の住所へ送付されます。
送付時期は自治体により異なり、例えば北海道函館市の場合は申込完了日から2週間程度で届きます。寄付金受領証明書はふるさと納税の寄付を自治体が証明する書類であるため、確定申告まで大切に保管しておきましょう。
STEP5.確定申告を実施する
ふるさと納税で控除を受けるには、住所地の所轄税務署での確定申告が必要です。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算する手続きです。
すでに源泉徴収された税金がある場合は、その過不足を精算します。通常、自営業者などがする手続きで、会社員で収入が給与のみの場合は会社で年末調整するため、確定申告の義務はありません。
確定申告書を作成して提出をしなければ、ふるさと納税による控除を受けられないため注意しましょう。ふるさと納税をした、翌年3月15日までに寄附を証明する書類(受領書)をあわせて提出します。
※参考1:ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ|総務省
※参考2:ふるさと納税をされた方へ 確定申告について ふるさと納税の控除の仕組み|総務省
STEP6.所得税の還付や住民税の控除を受ける
確定申告すると、ふるさと納税をした年の所得税から控除され、すでに源泉徴収などで所得税を納めている場合は税金が還付されることがあります。なお、還付金額は寄付者の年収や他の控除の状況などにより異なるため、一律ではありません。
住民税も、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
住民税の控除は、所得税のように還付金が口座に振込まれません。控除された分は、翌年度の住民税から差し引かれるので、5~6月に届く「住民税決定通知書」で控除額を確認してください。
会社員は、5~6月に会社から渡される「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税 特別徴収税額の決定通知書」で控除額を確認します。
不動産売却でふるさと納税する際の注意点

不動産売却でふるさと納税をする場合は、主に以下3つの注意点があります。
- ワンストップ特例制度は利用できない
- 譲渡所得が発生しなくても確定申告が必要
- 必要な提出書類を把握・保管しなければならない
ワンストップ特例制度は利用できない
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告しなくても寄付金控除を受けられる制度です。わざわざ確定申告する必要がないため、通常のふるさと納税では便利なシステムといえます。
しかし、不動産売却をして利益が発生した場合は確定申告が必要なため、ワンストップ特例制度を利用できません。
ワンストップ特例制度を受けられるのは、確定申告の不要なサラリーマンなどの給与所得者などであり、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
※参考:よくある質問|総務省
譲渡所得が発生しなくても確定申告が必要?
本来、譲渡所得が発生しない場合は確定申告する義務がありません。しかし、マイホームの3,000万円特別控除の特例の利用によって計算結果がゼロやマイナスになる場合は確定申告をしなければいけません。
また、マイホーム以外の不動産の売却損を他の不動産の譲渡所得と損益通算したい場合や、マイホームを売却して譲渡損失が生じたときに、他の所得との損益通算や繰越控除をしたい場合には、確定申告をする必要があります。
例えば、マイホームを売却した場合に譲渡損失が生じたとき、一定の要件を満たせば譲渡損失の分をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)できます。さらに譲渡損失が大きくその年に引ききれない場合は、以降3年間他の所得と損益通算することができます。
売却損の損益通算をすると所得が減ったりゼロになったりするので、ふるさと納税での寄付上限額が少なくなったり、ふるさと納税をしても税金の控除が全く受けられなかったりしますが、減税としては効果的です。
※参考:No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
必要な提出書類を把握・保管しなければならない
ふるさと納税で還付・控除を受けるには、様々な書類が必要です。確定申告を税務署の窓口で行う場合に、必要なふるさと納税関連書類として、以下のものが挙げられます。
- 源泉徴収票
- 寄付先の自治体が発行した寄附金受領証明書
- 個人番号確認の書類と本人確認の書類の原本またはコピー
ふるさと納税すると、寄付先の自治体が発行した寄附金受領証明書が住まいに送られてきます。自治体により発送時期には違いがあり、しっかりと保管する必要があります。
寄附金受領証明書は寄付した件数分の証明書が必要なため、複数回寄付した人は証明書がすべて揃っているかを確認してください。
令和3年分以後の確定申告は、特定事業者が発行する『寄付金控除に関する証明書(年間寄付額を記載した書類)』でも申請できます。この場合、1枚の提出で事足りるようになります。ただし、寄付回数が多いと複数枚になる場合があるので注意が必要です。
※参考1:ふるさと納税のやり方は?申し込み方法や必要な手続きを深掘り解説|ふるさとチョイス
※参考2:ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について|国税庁
不動産売却後のふるさと納税に関するよくある質問
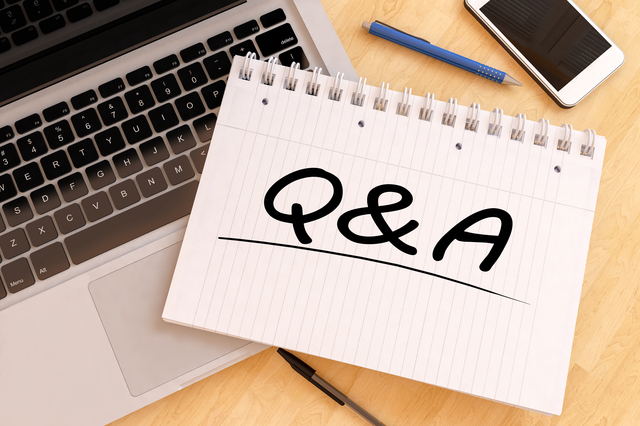
ふるさと納税を行う際には、さまざまな疑問がつきものです。ここでは代表的な2つの疑問について解説を行っていきます。
- 3,000万円控除とふるさと納税は併用できる?
- ふるさと納税しない方がいい人の特徴は?
3,000万円控除とふるさと納税は併用できる?
結論、3,000万円控除とふるさと納税の併用は可能です。
ただし、不動産売却で控除を適用したことで譲渡所得が「0」になった場合は、ふるさと納税を利用してもメリットを得られません。
そもそも『3,000万円控除』とは、マイホームを売却して利益が発生した場合、一定の要件に該当すれば譲渡所得から最高3,000万円まで控除される制度です。 したがって、3,000万円控除を適用しても売却益が出る場合にふるさと納税と併用しましょう。
※参考1:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁
※参考2:ふるさと納税のしくみ|税金の控除について|総務省
ふるさと納税しない方がいい人の特徴は?
ふるさと納税には税金を節約できるなどのメリットがありますが、活用しないほうがいい人もいます。ふるさと納税をしない方がいい人の特徴として、主に以下の2つが考えられます。
- ほかに優先すべき税制特例や控除がある
- 手元に現金がない
不動産売却をした年は、『マイホームを売ったときの3,000万円特別控除の特例』などを受けると譲渡所得税がかからない場合があるので、まずは税制優遇措置を優先しましょう。
また、ふるさと納税の寄付はいわば税金の前払いであるため、手元に現金がない場合は無理して利用しないほうがよいでしょう。
不動産売却後のふるさと納税はプラスになるかを確認しよう
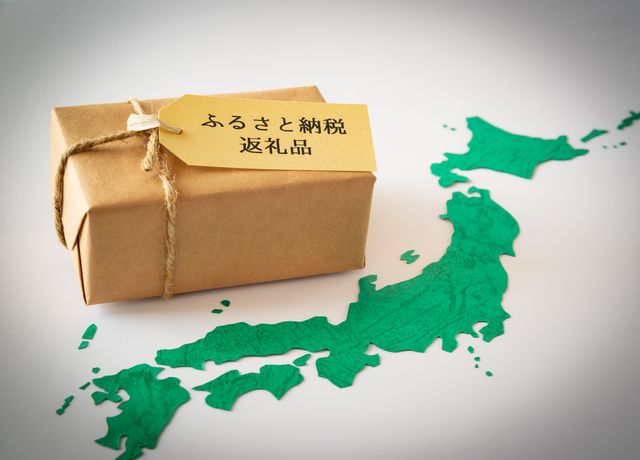 マイホームなどの不動産を売却するときは、一定の要件が備わっていれば3,000万円特別控除などを利用できるため、譲渡所得税がかからないことがあります。
マイホームなどの不動産を売却するときは、一定の要件が備わっていれば3,000万円特別控除などを利用できるため、譲渡所得税がかからないことがあります。
ただし、要件を備えていない、あるいは投資用不動産の売却などのケースでは、居住用の特例を利用できず譲渡所得税が発生するケースが考えられます。こうした場合には、ふるさと納税を活用し、メリットを得ることを検討してみてはいかがでしょうか。
記事監修
橋本 秋人(はしもと あきと)
FPオフィス ノーサイド代表。CFP®、1級FP技能士、終活アドバイザー。 大学卒業後、住宅メーカーで30年以上相続対策、個人の不動産活用、CREなどを担当。独立後はセミナー講師、執筆、相談、実行支援を中心に活動。 終活アドバイザー協会(NPO法人ら・し・さ)副理事長。日本FP協会評議員
・FPオフィスノーサイド
・NPO法人 ら・し・さ

