
長引く新型コロナウイルス流行の影響で金融機関への住宅ローンに関する相談が増えています。住宅金融支援機構によると、同機構に寄せられた住宅ローンに関する相談件数は、2020年3月で214件でしたが、4月には1158件、5月末までの累計数は2265件になっています。
なかには、住宅ローンの返済が困難になり、マイホームを手放さざるを得ない人もいると思われますが、そのようなときに利用されるのが「任意売却」という制度です。
「任意売却という言葉は聞いたことがあるけれど、よく分からない」という人や、なかには「競売や自己破産との違いが分からない」という人も多いのではないでしょうか。この記事では、任意売却の流れや競売・自己破産との違い、メリットなどについて解説していきます。
この記事で分かること
- 任意売却とは、どのような売却方法なのか
- 任意売却の流れ
- 任意売却と競売の違い
- 任意売却と自己破産の違い
- 任意売却で一般的にかかる期間
- 任意売却の条件やできないケース
もくじ
そもそも任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難となった場合に、借入れしている金融機関に合意を得た上で、物件を売却する方法です。
通常、金融機関は住宅ローンが全額返済されない限り、設定された抵当権の抹消に同意してくれません。抵当権が残ったままの物件を購入してくれる人はいないため、実質、売却ができないという仕組みになっています。
ただし、金融機関へ相談すると債務者の事情などを勘案し、返済計画を組み直すことにより、特別に売却を許可する場合があります。それが任意売却です。不動産業界では「任売(ニンバイ)」と呼ばれ、競売や公売と分けて取扱われています。
通常、住宅ローンを滞納してしまうと、期限の利益(債務者がローンを分割で返済する権利)が失われます。つまり、借入れをした人は、滞納すると残債の一括返済を要求されるという仕組みになっています。一括で返済できない場合、担保となっている不動産を競売にかけ、落札されると不動産は強制力を持って明け渡しを要求され、売却代金は債権者に渡ります。
しかし、競売は手間がかかる割には回収できる金額も限られており、金融機関としては避けたいのが実情です。競売は、「住宅ローンを延滞した債務者が話し合いに応じない」「不動産売却の意志を示さない」などの場合にとる最終手段とされています。
そのため、競売になる前段階で債務者より相談があれば、金融機関は任意売却をすすめることがほとんです。なぜなら、そのほうが債務者・債権者双方にとってメリットがある結果につながるからです。
このように、住宅ローンの返済が困難になった人にとって任意売却は重要な売却手段といえるため、事前に知識を持っておく必要があります。
任意売却について、まずは、以下の2点について押さえておきましょう。
- 任意売却の費用内訳
- 任意売却の計算方法
任意売却にかかる費用の内訳
任意売却は、通常の不動産売却と同様、売却に費用が発生します。
発生する費用は、主に以下の4点です。
- 仲介手数料
- 抵当権抹消登記費用
- 印紙代
- 契約書類発行費用
なお、上記以外にも一戸建てで、売主が建物を解体して更地で売却する場合には解体費用、家の清掃を専門業者に依頼したい場合はハウスクリーニング費用、測量費用などがかかるケースもあります。売主の希望条件や物件の状況によって発生する費用が異なることを把握しておきましょう。
【あわせて読みたい】
▶︎不動産売却にかかる手数料の相場と計算方法について
仲介手数料
仲介手数料は、不動産売買をするときに不動産会社に支払う手数料です。仲介手数料は成約価格により異なります。
本来は金額区分ごとに分けて計算する必要がありますが、速算式の場合は以下のとおりとなります。
| 金額 | 計算式 |
|---|---|
| 成約価格200万円以下 | (成約価格×5%)+消費税 |
| 成約価格200万円超400万円以下 | (成約価格×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超の部分 | (成約価格×3%+6万円)+消費税 |
抵当権抹消登記費用
そもそも抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利を指します。
抵当権抹消登記費用は、登記簿謄本に記載された抵当権の内容を削除する際に発生する費用となり、費用の内訳は以下のとおりです。
【抵当権の抹消登記費用】※土地1筆、建物1つ/司法書士に依頼する場合
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の個数(土地1筆、建物1つ)×1,000円=2,000円 |
| 司法書士の報酬 | 1万5,000〜2万円+消費税 |
| その他(登記簿謄本や郵送費など) | 2,000円程度 |
| 合計金額 | 2万〜2万5,000円程度 |
上記の表で紹介した費用内訳は、あくまで概算となりますので、参考程度にしておきましょう。
印紙代
印紙代は、契約書に記載された契約金額により税率が変わります。国税庁の「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」に記載されている一覧は以下のとおりです。
| 契約金額 | 印紙代 |
|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 5,000円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
※国税庁 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置より編集部作成(2024年3月31日までの軽減措置を適用)
契約書類発行費用
任意売却時は通常の不動産売却と同様に、さまざまな契約書類を公的機関に発行依頼しなければならず、その費用が発生します。
主な契約書類と費用の目安は以下のとおりです。
| 契約書類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | 300円 |
| 住民票 | 300円 |
| 固定資産税評価証明書 | 400円(※) |
※1件のみの場合(平成30年5月1日より2件目以降は100円/件)
上記はあくまで契約書類の一例です。 表のように、自治体で取得する書類の費用は300〜400円程度で済みますが、たとえば調査費用も含む土地の測量図を取得する場合などは、10万円以上と高額になる場合もあるため注意しましょう。
任意売却にかかる費用の総額
これまで解説してきた任意売却の場合にかかる費用を合計すると、その総額は売却価格の4〜6%程度になるのが一般的です。
なお、先述のとおり費用は通常の不動産売却でも発生します。特別に弁護士などの代理人を依頼しなければ、任意売却だからといって費用が高くなるということはありません。
任意売却の場合、諸費用は事前に債権者へ相談しておけば、売買代金のなかから支払うことが認められます。
任意売却にかかる費用の計算方法
任意売却にかかる費用の計算方法は、主に以下の3項目を合算することになります。
- 仲介手数料
- 抵当権の抹消費用
- 印紙代
たとえば、売却価格が3,000万円となった不動産の場合の費用を見ていきましょう。なお、抵当権の抹消登記費用は司法書士に依頼し、2万1,000円(税込み)となった場合を想定しています。
- 仲介手数料:(3,000万円×3%+6万円)+消費税=105万6,000円
- 抵当権の抹消登記費用:2万1,000円
- 印紙代:1万円
上記の金額をあわせると、売却価格3,000万円の不動産を任意売却した場合の費用は、108万7,000円となります。
ただし、これらはあくまでも概算であるため、参考程度にお考えください。測量費や残置物(荷物)の処分代などが発生する場合は、さらに費用がかかるので注意しましょう。
任意売却の流れ

ここでは、任意売却の実際の流れについて見ていきましょう。具体的には、以下ステップで任意売却は行われます。
- 金融機関へ申入れ
- 売却査定
- 債権者(金融機関)と相談
- 任意売却開始
- 売買契約の成立
- 不動産の引渡し
任意売却は通常の不動産取引と比べ、債権者である金融機関が深く関わる取引です。分かりにくい部分もあるので、順番に解説します。
1.金融機関への申入れ
住宅ローンの返済が困難になった際に、最初に行うのが金融機関への申入れ(相談)です。
すでに住宅ローンを滞納して金融機関より督促が来ている場合は、決して無視しないでください。万が一無視してしまうと、いきなり競売という手続きでマイホームを失うことにもなりかねません。
まずは、支払いが困難であり任意売却を検討している旨、金融機関の担当者に正直に申出てください。その際、他の金融機関などからも借入れがある場合は、あわせて申告しましょう。相談を受ける側である金融機関も同様の相談には慣れており、強引な取り立てや無理な返済を要求することはありません。
2.売却査定
金融機関に連絡をした後は、不動産会社に売却査定の依頼をすることになります。
ここでの注意点は、任意売却をした実績が豊富な不動産会社を選ぶことです。任意売却は、債権者との交渉や、滞納状況の相談、スケジュール管理など、通常の不動産取引では発生しない業務があります。
任意売却は時間との戦いでもあるため、スムーズな取引をしてもらえそうな不動産会社を選びましょう。また、金融機関によっては、最初の相談時に任意売却を検討している旨を伝えると、不動産会社を紹介してもらえるケースもあります。
【あわせて読みたい】
LIFULL HOME'Sで任意売却の相談を依頼した後の流れ
3.債権者(金融機関)と相談
査定額が算出されたら、債権者(金融機関)との相談というステップに進みます。一般的に、この交渉は不動産会社が代行します。
債権者が複数の場合は各社に連絡し、査定額・予想売却価格を伝え、おおよその金額を提示します。このときに承諾を得られなければ、売却はできません。
とはいえ、金融機関側も競売より任意売却をすすめたいと考えるケースがほとんどです。そのため、売出し価格を承諾してもらえるかの判断をしてもらうことになります。
なお、この際に売主が売却代金から、売却にかかる諸費用や引越し代金を捻出したい場合は、その旨をあらかじめ交渉する不動産会社に伝えておきましょう。
4.任意売却開始
債権者から売却の承諾を無事得ることができれば、売出しが開始されます。
任意売却の場合も通常の売買と同じように、民間の不動産ポータルサイトや、不動産会社同士で情報を共有するサイト「不動産流通機構」に情報が掲載されます。ただ通常、任意売却であることは、不動産サイトやチラシ広告などには記載しません。
しかし、購入希望者には、あらかじめ任意売却物件である旨を伝える場合がほとんどです。なぜなら、購入希望者が実際に買主となる場合、手付金の保全や不動産に欠陥があった際の瑕疵担保責任など契約に関係する事項に関わるため、購入するか否かの重要な判断事由になるからです。
5.売買契約の成立
買主より購入申込みがあった場合、売買契約日・決済日・引渡し日を決め、売買契約を締結することになります。
なお、購入申込みの時点で売買金額の交渉があった場合、債権者と再度交渉することになります。買主の提示した金額で受諾するか否かを判断するのです。
なお、この際の決定権は売主にはなく、あくまでも債権者が決めることになります。債権者が多い場合は、交渉に時間がかかることもあり、その間に買主の気持ちが変わってしまうケースもあります。
すべての交渉がまとまったら、売主・買主・仲介会社が集まり、重要事項の説明及び売買契約書の記名・押印を行います。
6.不動産の引渡し
不動産の売買契約が完了すると、売主はすぐに引渡しの準備に入ります。
売買契約締結後も、ゆっくりすることはできません。なぜなら、債権者との話し合いによって競売までの期日が決まっているからです。期日までに不動産の引渡しができない場合は、競売へ強制的に移行してしまいます。
買主は借入れ先の金融機関に住宅ローンの審査を依頼し、承認を得られればすぐに決済手続きに移ります。このとき、売主も速やかに転居の準備をします。任意売却は、契約手続きをしたら終わりではなく、残金決済までのスケジュールが厳しく管理されます。売主・買主にとって契約から決済(引渡し)までは慌ただしい期間となるでしょう。
なお、引渡し猶予の特約を付けていれば、決済後すぐに家を引き渡さなくても、決済後7日前後は引渡しを待ってくれるケースもあります。
任意売却と競売の違い

任意売却と競売の主な違いは、以下の表のようになっています。
| 任意売却 | 競売 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 価格の相場にほぼ近い | 価格相場の50〜60%程度 |
| 引越し費用などの捻出 | 交渉によっては確保可能 | 自己負担 |
| 住み続けられるか? | 相談可能 | 落札者が決定 |
| プライバシー | 情報は公開されない | 競売物件として公開 |
| 税金などの滞納 | 任意売却時に精算 | 支払い義務が残る |
| 売却期間 | 3~6ヶ月程度 |
6ヶ月~8ヶ月程度 (競売手続きに沿って進められる) |
| 仲介手数料 | 必要 | 不要 |
任意売却と競売は同じようなイメージがありますが、実際の内容は上記のように大きく異なります。住宅ローンの支払いが困難になったら、競売ではなく任意売却を選択できるようにしましょう。
以下で、それぞれの項目について解説していきます。
売却価格
任意売却は一般市場で売却するため、売却価格は通常の売却とそれほど差のない金額で決まることが多くあります。
競売の場合、買主は物件の調査が不十分なため、住宅ローンなどが使えず、不明点が多いままで購入しなければならないこともあります。そのため、一般の人が購入することはほとんどないでしょう。
競売は不動産会社などの法人か、あるいは安く仕入れたい投資家などが入札しますので、成約価格は任意売却と比較して安くなる傾向があります。
引越し費用などの捻出
任意売却は、事前に行われる債権者との交渉の際に、引越し代などについて話し合う機会があります。
一方、競売の場合、所有者が必要とする一切の費用は考慮されません。そもそも競売は、所有者へ相談されることはほとんどなく、決定事項の報告のみになります。所有者は金銭のやり取りはもちろん、取引の当事者として関わることはなく、退去日が通知されるのみです。
競売の場合は、裁判所主導による強制的な執行になるため、引越し費用として売却代金の一部を使用することはできず、引越し日なども都合にあわせてもらうことはできません。
住み続けられるか?
任意売却では、ケースによっては売主が元の住居に住み続けられる可能性があります。
例えば、一般の不動産市場に売出された物件を身内などに買い取ってもらう方法、リースバックなどの制度を利用する方法です。リースバックは、専門の会社にマイホームを一度買い取ってもらい、同じ会社と賃貸契約を結ぶものです。
一方、競売では落札されると、強制的に退去を迫られます。身内などに落札してもらおうとしても、他の入札者によって落札されてしまうこともあり、確実ではありません。
プライバシー
任意売却の場合は、売出しをするときに返済が滞っていることや、任意売却であることなど、プライバシーに関する事項が公に知られることは原則ありません。
任意売却を取扱う不動産会社も、売主側の事情を理解しており、プライバシーに配慮した販売活動を行ってくれます。ただし、買主など特定の利害関係者には告知します。
競売の場合は、裁判所運営の情報サイトなどに詳細な住所まで掲載されます。外観や室内写真も公開されるので、プライバシーを守ることは困難です。
税金などの滞納
税金や社会保険を滞納すると、不動産が差し押さえられ、登記簿謄本にも記載されてしまいます。
任意売却の場合は、この差し押さえを抹消しないと売却できません。そのため、債権者は抹消のための費用として、売却価格からの支出を認めてくれます。
一方、競売の場合、売却代金は競売費用と住宅ローンの返済に充てられ、不動産を手放した後も、税金滞納などの記録はそのまま残ることになります。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産を売却する際に不動産会社に支払う手数料です。
任意売却の場合は、仲介会社を通して売却するため費用の負担があります。先述のとおり、売買契約価格を400万円以上とすると、仲介手数料は速算式を用いて「売買契約価格×3%+6万円+消費税」となります。
一方、競売の場合は仲介会社を通さずに裁判所の主導で売却するので、仲介手数料は不要です。
【あわせて読みたい】
任意売却と競売の違い
任意売却と自己破産の違い
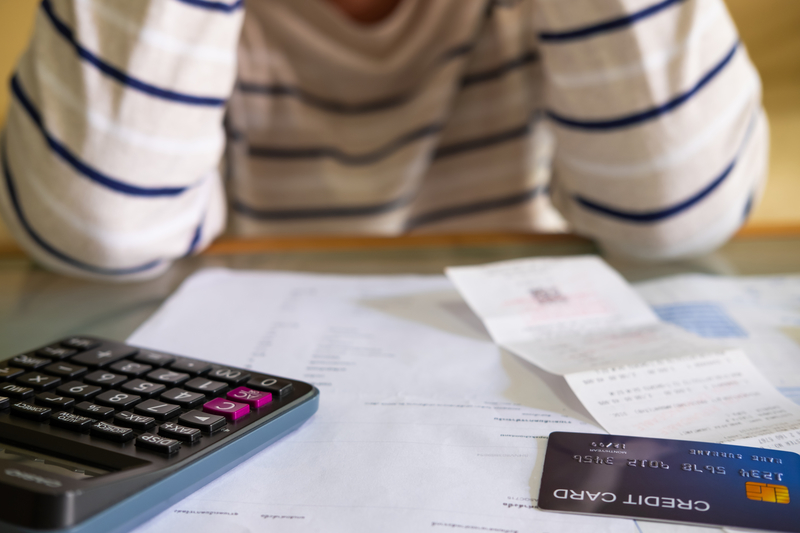
ここでは任意売却と自己破産の違いについて解説します。いずれも経済的に困窮したときに検討する選択肢ですが、それぞれの違いを理解しておく必要があります。
まず、任意売却とは住宅ローンの返済が困難になったときに、債権者の同意を得て不動産を売却し、返済に充当する手続きです。
一方、自己破産は、住宅ローンに限らず消費者金融などの借入れがあり、返済が困難となったときに、裁判所に申し立てて債務の弁済を免除してもらう手続きです。
ここでは、どちらの手続きを選んだほうが良いのか、解説します。
任意売却したほうが良い場合
任意売却を選んだほうが良い場合とは、定期的な収入があり自立した生活を続けられる見込みがあるときです。
自己破産が裁判所に認められると、住宅ローンのみならず、その他の債務も免責されます。しかし、その免責を受けるためには、所有不動産の売却だけではなく、自動車や貴金属などの所有財産を手放さなければなりません。
一方、任意売却の場合は、手放さなければならないのは不動産だけで、他の財産については処分せずに済みます。ただし、任意売却は不動産を売却した後も、払い切れなかった債務は残り、支払いを続けなければなりません。もちろん売却後の返済は、経済事情を勘案し、返済に窮しないように配慮した計画になります。
不動産こそ失ってしまうかもしれませんが、生活水準は大きく落とす必要もないため、まずは自己破産の前に任意売却を選択することをおすすめします。
自己破産したほうが良い場合
自己破産を選択したほうが良い場合は、住宅ローンだけではなく、消費者金融などに多額の借入れがある状態です。自己破産は、債務に比べ明らかに財産、収入が不足し、返済の見込みがない場合に裁判所に申請し、返済の免除を認めてもらう制度です。
自己破産すると、自宅の売却はもちろん、自動車や貴重品など売却し、弁済に充てることを求められます。また、自己破産してから一定の期間は、特定の資格の保持や他人の財産に関わる仕事に就くことが制限されます。
そのため、自己破産は国民すべてに認められた権利ですが、あくまでも最終手段とお考えください。なお、養育費や税金などの非免責債権もあるため、すべての債務をゼロにできるわけではありません。
【あわせて読みたい】
自己破産しても払わなければいけない債務とは
任意売却のメリット・デメリット

ここからは、任意売却のメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
以前は、住宅ローンの返済が困難であると競売になり、強制的にマイホームを失う事例が多くありました。しかし、2012年から競売の件数は低減してきており、2022年現在では多くの人が任意売却を選ぶようになっています。
これはインターネットを中心に、住宅ローンが滞った際の情報が広がり、競売になる前に任意売却を選ぶ人が増えてきたからだと考えられます。
※参考:一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR)「競売物件統計データ(2019年)」
任意売却のメリット
任意売却を選ぶメリットは主に以下が挙げられます。
- 市場価格と同程度の価格で売ることができる
- 残債を分割返済にできる
- 交渉次第では引越し費用を融通してもらうことができる
- プライバシーが守られる
1つ目のメリットは、市場価格と同程度の価格で売れる点です。
競売の場合、「売出されている物件の室内を見ることができない」「リフォーム費用をあらかじめ見積もることができない」「競売開始から落札日までの期間が短い」などの理由から落札者の負担が大きく、市場価格の5〜7割程度で取引されてしまう傾向にあります。
一方、任意売却であれば物件の室内を見ることができる他、競売よりも売却期間での自由度が増すため、売却活動に十分な時間を充てられるでしょう。その結果、じっくりと購入希望者を選ぶことができ、自身の希望価格に近い価格で売却できる可能性があります。
2つ目のメリットは、売却後も支払いは続くものの、残債を分割返済にできる点です。
家を売却した場合、原則として住宅ローン残債は一括返済しなければなりません。先述のとおり、競売の場合は市場価格の5〜7割程度で取引されてしまうため、売却益を住宅ローンに充てたとしても、残債が発生するケースがほとんどです。
一方、任意売却であれば残債が発生していたとしても分割返済することができます。したがって、住宅ローンにおける毎月の負担額は軽くなるでしょう。
3つ目のメリットは、債権者との相談時に交渉次第で、売却益から引越し費用を融通してもらえる点です。金融機関により異なりますが、10〜30万円程度が引っ越し費用として認められることもあります。
競売の場合はそういった制度が設けられておらず、引越し日時も決められているため、売主の事情は考慮してもらえないケースがほとんどです。
4つ目のメリットは、プライバシーが守られるという点です。
競売は裁判所主導で行われ、競売物件であることがインターネット上に公開されるため、不特定多数の人の目に触れることになります。
任意売却の場合は、買主など特別な利害関係者以外にローン滞納などが知られることはありません。特に子どもがいる家庭にとって、プライバシーの配慮は今後の生活をしていく上でも重要な項目であるため、大きなメリットといえるでしょう。
任意売却のデメリット
任意売却には、デメリットもあります。当然ですが、住宅ローンが延滞した時点で個人信用情報に記録が残り、当面は住宅ローンを組むことやクレジットカードの作成が困難になります。
それ以外にも、以下のようなデメリットが挙げられます。
- 住み慣れたマイホームを手放さなければならない
- 手続きの負担
- 離婚時などは配偶者とコンタクトを取らなければならない
- 連帯債務者・連帯保証人に説明しないといけない
1つ目のデメリットは、住み慣れたマイホームを手放さなければならない点です。
任意売却の場合、リースバックという仕組みを利用して、売却した物件に住み続けることが可能な場合もあります。リースバックとは、一度不動産会社(リースバック会社)に物件を売却した上で、賃貸借契約を結び、住み続けるというものです。
しかし、どのような不動産でもリースバック会社に購入してもらえるというわけではありません。そもそも、買取り価格が市場価格より安くなるため、債権者に承諾してもらえないことがあり、適用にはハードルがあります。そのため、住み慣れたマイホームを手放さなければならない可能性は高いでしょう。
2つ目のデメリットは、手続きに関する負担が生じる点です。
任意売却を行う際には、不動産会社への依頼や内覧の立ち合い、金融機関への連絡、売買契約の締結など多くの手間や時間がかかります。
3つ目のデメリットは、離婚などで任意売却する場合、不動産が共有不動産であれば、かつての配偶者に連絡を取らなければならないことです。
離婚協議などで揉めてお互いが感情的になっているケースでは、「売却の手続きが思うように進まない」ということもあります。
4つ目のデメリットは、連帯債務者・連帯保証人を立てる場合に任意売却における詳細について説明しなければならないことです。
住宅ローンが滞ると連帯債務者・連帯保証人は代位弁済の義務があります。任意売却する場合は、金融機関との話し合いの経緯や、今後の返済計画など、あらかじめ説明しなければなりません。
親しい人にこのような金銭的な話をするのは、大きなストレスとなることでしょう。
任意売却で一般的にかかる期間

任意売却にかかる期間は、その不動産の種別や売却の時期、エリアなどさまざまな条件に影響を受けます。
任意売却において、それぞれの工程でかかる期間は一般的には以下のようなになっています。
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 金融機関からの督促 | ローン滞納後1~2ヶ月 |
| 不動産会社の選別と不動産価格査定 | 約2週間 |
| 債権者への確認 | 約1~3ヶ月 |
| 任意売却の開始~売買契約締結まで(売却期間) | 約3~6ヶ月 |
参考までに一般の不動産取引での売却期間は、以下のようになっています。

※参考:「不動産の売却どうしたらいい?経験者3,000人のデータからわかる、リアルな売却傾向(住まいの売却データファイル)」
LIFULL HOME'Sにおける「住まいの売却データファイル」の統計では、通常の不動産売却では、半数以上の人が6ヶ月以上要している、ということになります。
任意売却の売却期間は約3〜6ヶ月と、通常の不動産売却における期間より短いといえますが、先述のとおり競売よりも売却期間での自由度が増すため、売却活動に十分な時間を充てることができるでしょう。
任意売却の条件やできないケース

任意売却の手続きを行うためには条件があります。ここでは、任意売却の条件と手続きできないケースを4つを挙げて解説します。
- 保証会社による代位弁済
- 担保権者全員の同意
- 売却額が住宅ローン残高よりも大幅に低い
- 所有者本人の同意
保証会社による代位弁済
金融機関によっては、保証会社による代位弁済後でないと、任意売却ができないケースがあります。代位弁済とは、債務者がローンを滞納すると、債務者に代わって金融機関に返済することをいいます。
金融機関によっては債務者からの任意売却の申し出を受けるより、保証会社から代位弁済により一括で支払いを受けるほうが得と考えることがあります。その場合には、代位弁済の前段階で金融機関に相談しても「代位弁済後に保証会社と交渉してください」と言われることがあります。
しかし、住宅ローンの種類や金融機関によっては、そもそも保証会社を付けていないケースもあります。よって、どのタイミングで任意売却の手続きができるかどうかは、ケースバイケースとなります。
担保権者全員の同意
担保権者とは、対象不動産に設定されている抵当権の権利者(債権者)のことです。複数の抵当権が付いている場合は、全員の同意が必要です。
ここでいう「同意」とは、「残代金を全額支払う前に抵当権を抹消しても良い」という同意です。この同意がないと、不動産の売却時に抵当権の抹消ができないため、売れなくなってしまいます。
なお、抵当権者ではない消費者金融やカード会社のような一般債権者には任意売却の同意は必要ありません。
売却額が住宅ローン残高よりも大幅に低い
売却額が住宅ローン残高より大幅に低い場合は、担保権者の同意が取れず、任意売却ができません。任意売却では、担保権者(債権者)との相談の段階で、査定書を基に売却予想金額が提示されます。この金額がローン残高に比べ、大幅に低い場合は否認されてしまうのです。
任意売却は、不動産を売却した対価をローン返済に充て、それでも払い切れない分はその後、債務者が時間をかけて支払います。しかし、あまりに返済額が大きく残ってしまうと、完済することが現実的ではなくなるため、担保権者は承認しないということになってしまうのです。
所有者本人の同意
最後に、任意売却は所有者(売主)の同意が必要です。これはどういうことかというと、任意売却はその名のとおり、所有者の「任意による売却」を指します。
任意によらない売却は「競売」です。競売は裁判所主導による売却で、所有者がどんなに嫌がっても、強制的に進んでしまいます。
任意売却は専門的な知識のある不動産会社へ早めの相談を

任意売却の対応をできる不動産会社は、専門的な知識のある会社に限られます。そのため、依頼時には、知識や経験が豊富なスタッフがいることや、実績がある会社を選ぶことが大切です。
任意売却の流れを理解し、複数社の不動産会社に依頼しながら適切に進めていきましょう。具体的には、一旦3〜5社程度を目安にして比較検討することが望ましいです。
とくに、住宅ローンの返済が困難になった方は、「競売」や「自己破産」などよりもまずは「任意売却」ができないか調べることから始めましょう。
任意売却の重要なポイントは、「時間」です。大切なマイホームを失う可能性もある任意売却ですが、それでも手続きが上手くいけば、経済的な再建の道筋が見える場合がほとんどです。
担保権者(債権者)を交えた売却のため、通常の売却よりも手間やストレスもあるかと思いますが、それを軽減してくれるパートナーが不動産仲介会社です。
LIFULL HOME'Sでは、任意売却の取扱いをしている会社への依頼を承っています。「任意売却について検討している」「一度相談をしてみたい」という方は、ぜひご相談ください。
記事監修
赤松 昭彦(あかまつ あきひこ)
宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を保有。不動産売買仲介会社で8年間勤務。現在は医師・歯科医師向けの不動産コンサルティング業務に従事している。

