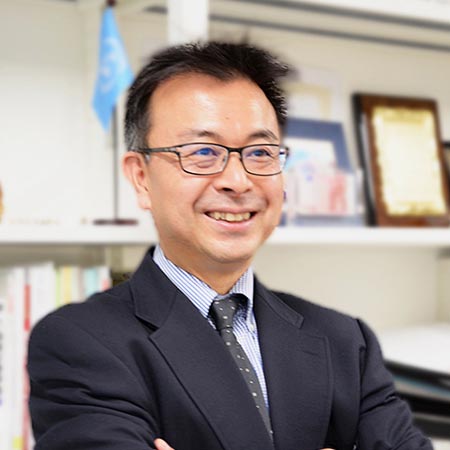生産緑地法改正が残した傷跡①
2022年問題と呼ばれる市街化区域内農地の問題を考えるにあたり、1991年の法改正当時の法改正の背後にあった問題と、当時の農地所有者の意思決定行動について整理してきた。
このような法改正の政策的な問題は、改正後の5年後過ぎたころから多くの自治体が、様々な問題を引き起こしていた。本来であれば、都市の内部においては、個別的な農地所有者の最適化行動を地域全体での最適化へと誘導しなければならなかった。つまり、既存の土地利用と共に、選択された生産緑地・宅地化農地を融合させ、長期均衡的下の最適な土地利用形態へと誘導していくことが求められていたのである。
生産緑地法改正によって、宅地化すべき農地と保全すべき農地が明確に分離され、宅地化すべき農地に対しては、固定資産税・都市計画税が宅地並に課税されるとともに、相続税の納税猶予制度からはずされることとなり、都市農地をめぐる税制の適正化は、一応実施されたこととなった。しかしながら、これからの課題としては、需要と供給の市場原理の中から創出された宅地ではなく、生産緑地法改正と税制改正といった政策ショックによって一度に創出された宅地を、どのように土地利用を転換させ、既存の土地利用形態と保全すべき農地との融合を図りながら、良好な都市空間を創造していくのかといった問題に直面したのである。
つまり、既存の土地利用形態と保全すべき農地を与件として、動態的に変化する宅地化農地の誘導を、計画によってどこまで規制できるかどうかといった問題を各自治体は解決しなければならなかった。
しかし、そのような政策は必ずしも十分に機能しなかった。その原因として、いくつかの問題が指摘された。
まず、宅地化を選択した農地を宅地へと転換していくためには、公的部門においては公共基盤整備を実施しなければならない。基盤整備が不十分な地域において、宅地が創出されたとしても、宅地としての機能を十分に持たせることは困難であるとともに、無秩序な環境形成が行われることとなる。不十分な都市基盤整備を今後どのように改善していくのか、またはその財源をどのように調達するのかといった問題が指摘された。
いわゆる公共施設の整備、インフラの供給問題である。
生産緑地法改正が残した傷跡②
名古屋市のような都市基盤整備が既に整っている自治体においても、新しい問題に直面した。
名古屋市においては、市街化区域の大半が区画整理済みであり、基盤整備は整っているものの、そのような区画整理・耕地整理済の地域の中に、約4500-5000haの低未利用地を残していた。さらに、生産緑地法改正によって、1470haの宅地化すべき農地が追い打ちをかけるようにでてきた。
また、今回の法改正によって創出された宅地化農地は、市街化区域においても都市近郊地域であり、都市基盤整備水準が低く、交通条件等が相対的に悪い地域から創出されたこととなる。さらに、当時の名古屋市は、人口が流出傾向にあり、宅地需要は減少していた。そのような中において、どのように土地の有効利用を促進させていくべきなのかといった問題と共に、計画当事者が最適な土地利用像について、解を導出できないといった問題が指摘された。このような問題は多くの自治体が抱え、その後の都市の縮退に迎えた地域では、空き地・空き家問題のきっかけとなってしまったのである。
さらには、生産緑地法改正による土地利用の選択は、農地所有者の意向を尊重するかたちで実施されたため、無秩序な開発を生むこととなった。
それは、都市計画決定後の区画整理区域内における市街化区域内農地においても同様であり、そのような農地が生産緑地指定を受けることにより、区画整理事業の計画自体の変更が余儀なくされることとなった。つまり、当初描いた都市計画の姿を変更させる必要が生じたのである。計画の変更を伴った地域における保全すべき農地をどのように融合させ、当初ねらった開発利益をどのように具現化していくのかといった問題が指摘された。
また、農地所有者の意向を尊重するとともに、一筆毎の意向にもとづき決定されたため、宅地化農地がモザイク状に(虫食い的に)分布することとなった。そのような状況は、宅地への土地利用転換だけではなく、農業の継続に対しても影響を与えるものである
生産緑地法改正が残した傷跡③
宅地化農地の土地利用転換手法として、緑住ミニ区画整理事業、定期借地権制度、地区計画制度、特定優良賃貸住宅供給促進事業などの制度の活用の可能性が考えられた。
しかしながら、これらの制度には、いくつかの問題を残すこととなった。まず定期借地権制度は、未だその利用については地域的に限界があり、土地価格の絶対水準が高い都市においてのみ機能した。また地区計画制度は、土地所有者の意思を尊重しながらすすめていくために、地域としての合意形成を確立するのに大きなエネルギーが必要とされた。緑住ミニ区画整理事業の実施には、一定規模(0.5ha以上)の規模が必要とされたためその利用は限定的となった。
加えて、宅地化農地を賃貸住宅へと誘導する手法として、特定優良賃貸住宅供給促進事業・定期借地権制度などが用意された。しかしながら、特定優良賃貸住宅供給促進事業等の活用は、農協などにおいて必ずしも奨励していなかった。貸家住宅への需要量が限定される中では、新規の供給の発生により供給過多となることが予想されたためである。農地所有者は、既に不動産経営を行っていたため、より好条件の賃貸住宅が供給された場合においては、住み替えが起こるだけに過ぎず、現在の不動産経営を圧迫する可能性も指摘されていた。それゆえに、住宅・宅地の供給拡大を積極的に行おうとする傾向は小さかった。
2022年問題は起こるのか?
1991年の生産緑地法改正と地方税法の改正後、30年が過ぎようとしている。前述のように、法改正が実行された当時から、多くの課題を抱えていた。
生産緑地法の改正は、都市における開発速度を上昇させたため、都市内部においては、多くの問題を発生させてしまったのである。長期均衡下における最適土地利用へと誘導していくためには、市場原理にゆだねておくことには限界があり、早急な政策介入が必要であったが、そのような政策が投入されることはなかった。その結果として、現在の空き地・空き家問題を促進させてしまったといっても過言ではない。
生産緑地法の改正及び地方税法の改正によって、都市農地を巡る問題は、大きな転換期を迎えた。そして、30年後過ぎようとしている中で、新しい課題に直面しようとしている。生産緑地法改正における保全すべき農地と宅地化農地の選択は、土地所有者の意向を尊重するかたちで実施された。そのため、地域全体としてのバランスを考えた土地利用に関する判断が実施されたわけではなく、各土地所有者の個別の事情によって土地利用選択が実施された。そのため、生産緑地法改正の対象となったほとんどの都市においては、宅地化農地が虫食い状に出現など、土地利用計画上の多くの問題を持つことに至ったのである。
また、各宅地化農地においても、農地所有者は、土地利用転換の手法・土地利用意向ともに、それぞれ異なった意向を示しており、一団のまとまった土地として、土地利用転換を実施することは困難であった。しかしながら、地域全体として最適な土地利用を実現するにあたり、各土地所有者にその意志決定を委ね、すべての土地所有者の意向を尊重することはそもそも不可能であった。最適な土地利用を実現するためには、策定された土地利用計画を、公共部門による計画に基づいて、誘導変化させることが必要であった。
そのような制度は、依然として持ち合わせていない。さらには、バブル対策として実施されたこのような法改正は、今では、日本の多くの都市で人口減少と高齢化といったダウンサイジング問題に直面している。そのような中で、空き家問題は社会問題化しているのである。
2022年に、当時において生産緑地として指定された市街化区域内農地が宅地へと転換することが可能となる機会が提供される。その時に、農地所有者はどのような意思決定行動をとるのであろうか。それぞれの所有者がとる最適化行動は、都市農業そのものの生き残りができない中では、また将来のさらなる成長が期待しづらい中では、宅地化を選択するということが正しい選択であろう。将来に対する転換のオプションを保留し続けるということは、縮退する社会では合理的ではない。
しかし、その選択は社会にとっては、都市にとっては、さらなる社会課題を創出させてしまうことも確かである。住宅市場には、必ずしも歓迎すべき効果は出てこないものと考える。そのような中で、政府・自治体がどのような政策を策定してくるのかは、我々は慎重に観察していかなければならないであろう。