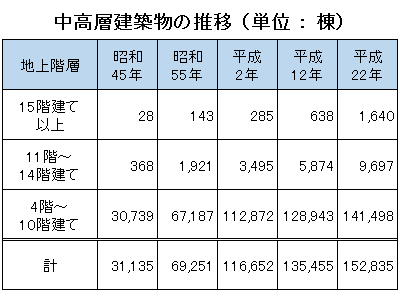高層ビルはさまざまな外部不経済を引き起こす可能性がある
「都市再生に貢献し土地の高度利用を図る」という名目で、都市再生特別地区など容積率・日影規制の緩和策が講じられた。その結果、消防庁の統計によると東京には15階建て以上の高層建物が、平成2年では285棟だったところが平成22年では1,640棟に急増し、都市環境を大きく変貌させている。
しかし東京のように、モンスーン気候かつ地震多発地帯に位置し、公平性を尊重してきた社会にとっては、こうした高層ビルはさまざまな外部不経済を引き起こすばかりで、全体の社会厚生を高めることはない。
要するに東京の都市環境においては、タワーは都市公害の元凶になる。この公害が深刻化し、将来世代に負の都市遺産を残さないためにも、速やかに高層化を促す政策群を転換すべきではないだろうか。
この外部不経済について金額として計算するために、モデルとして、ある臨海部のタワーマンション(※建蔽率80%、容積率400%、敷地面積10,878m2、延床面積161,697m2、間口86m、高さ179m、総戸数1,420戸、住戸平均専有面積78.5m2、平均単価96.2万円/m2)を例にとって検証してみた。
気候対応の面からみる外部不経済性
東京はモンスーン気候帯に位置する。年間平均気温は16℃、冬の数か月を除けば最低気温も10℃を上回っている。年間日照時間は1,881時間、夏至の太陽高度は78度と日照が厳しく、真夏日は45日(2014年)に及ぶ。
このモンスーン気候に適するように、夏の日射が壁・室内に当たらないように庇を伸ばす、屋根裏で瓦屋根のうけた熱気を逃がす、開口部を大きくとって風を通す、といった特長を備えた建築がつくられてきた。徒然草に「家のつくりやうは夏をむねとすべし」と言われるとおりである。
一方、高層ビルは、壁面・屋上も直射日光に晒し、巨大な壁面は周辺の風通しを塞ぐ。こうしたモンスーン気候にそぐわないインターナショナルスタイルの建築は、ヒートアイランド現象やゲリラ豪雨、遮風などの外部不経済を招いている。
①輻射熱
東京は100年で気温は約3℃上昇した。夕涼みが死語になるのも分かる。
この気温上昇のうち2℃は土地利用の変化(草地が舗装・宅地等に転換)、1℃が建築物の効果(壁面の輻射熱、躯体の蓄熱等)に由来し、建築物の効果は主に夜間の温度上昇、つまり熱帯夜を引き起こす。環7内側の宅地面積18,929ha、建蔽率53.9%、その建物余地の50%を緑化して気温を1℃下げるとすると、1℃当たり26,745円/m2として約11,696億円かかる。
街並みから突出している15階建て以上の建物がもっぱらこの輻射熱を起こすと仮定すると、一棟当たりざっと7.1億円の外部不経済を生じると計算できる。
②ゲリラ豪雨
昨年、都内でゲリラ豪雨が96回観測された。この原因も一部高層ビル群にあると推測されている。高層ビル群に湿った風が吹き込むと、風の流れが変わり、ビルの風下側に向けて上昇気流が起こる。そのため、積乱雲が発生しやすい状況が生まれるという。この豪雨対策に、都は貯水池に540億円投じ、さらに40年間も毎年250億円投じる必要があると主張する。総額1兆円、これも高層ビル(15階建て以上)1棟当たりにして約6.1億円の外部不経済がある。
③遮風
夏の日中、海風の温度は市街地より3~5℃低い。都市の風通しが良ければ、この海風がヒートアイランドを防いでくれる。室内に適風が抜ければ、体感温度で7~9℃も下げられる。こうした風環境を生かすように、日本家屋は大きな開口部を設け、障子や襖を外せば内外一体になる空間構成であった。
しかし、こうした風の道を塞ぐように、高層ビルが建ち並ぶ。風洞実験によれば、夏の日中の海風を汐留の高層オフィス群が遮り、上空風速6m/秒に対してビルの裏側では風速変化比0.2(風速1.2m/秒)以下の領域が広がることが確認されている。この風を塞ぐ範囲は、階高の5倍に広がる。
風通しの代わりに、植物の蒸散効果で涼しくしようとすると、密集市街地(建蔽率80%)において建物余地の50%を緑化するとして体感温度を元通りに下げようとすると、13.2億円が必要になる。つまり、このタワー1棟の遮風作用で、13.2億円もの外部不経済が生じている。海風を塞ぐような計画をするものではない。
地震対応の面からみる外部不経済性
 古くなったマンションの区分所有者が解体と費用負担を全員で合意することは難しい。数十年後には管理費は滞納されて長期修繕積立金も不足し、スラム化しやすい。そうなると都内に荒廃したタワーが何か所もいつまでも建ち残る都市風景になる(写真は、香港オールドアパートメントの例 ※イメージ写真)
古くなったマンションの区分所有者が解体と費用負担を全員で合意することは難しい。数十年後には管理費は滞納されて長期修繕積立金も不足し、スラム化しやすい。そうなると都内に荒廃したタワーが何か所もいつまでも建ち残る都市風景になる(写真は、香港オールドアパートメントの例 ※イメージ写真)文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会(2004年)によると、南関東地域でM7クラスの地震が発生する確率は30年間で70%と推定されている。
ニューヨークや香港はプレートの上にあって地震の恐れがないため、高層建築を成立させやすいのとは、東京は対照的である。しかも地盤が弱い。ニューヨークでは強固な岩盤に支えられるが、東京は東半分が沖積低地の柔らかい地盤に位置し、堅い地盤に比べて揺れの大きさは3倍にもなる。本来は技術的・費用的に、無理なく高層ビルが成立するような地域ではない。そして都心周縁部には、地震火災によって大規模な延焼拡大の恐れがある木造密集地域が22,500hが広がり、約210万世帯が居住していることも忘れてはならない。
①スラム化
高層ビルは地震に弱い。高層ビルは、地震の揺れをしなりで吸収するように構造計算されている。50階建てであれば、しなりの固有周期は5秒。したがって周期5秒の長周期地震動にはこの建物は共振して、ゆっくり10分前後も揺れ続ける。長周期地震動に何度も襲われれば、免震構造も大きく揺れることは実験結果から明らかにされた。そうなると構造の弱い部分、例えば骨組みの梁の付け根、柱側の下にひずみが溜まり、模型実験では接合部12か所のうち3か所が破断した。実際の建物であれば、修復できず使用不能になる。骨組みの破断だけでなく、設備・配管の断裂、避難階段の分断等によってタワーマンションは居住不能になる。
この使用不能になった建物は、解体するにも高層ほど工期も工事費もかかる。解体費は坪5~9万円とすると、モデルでは24~44億円に及ぶ。一部居住不能となったタワーマンション、これらの区分所有者がこの解体と費用負担を全員で合意することは難しい。被災していなくても、数十年後には管理費は滞納されて長期修繕積立金も不足し、スラム化しやすい。そうなると都内に荒廃したタワーが何か所もいつまでも建ち残る都市風景になる。解体・撤去が自治体の負担となれば、1棟24~44億円の外部不経済になる。
②火災旋風
それでも高層ビルは耐火造で公開空地も設けられているので、周辺の木造密集地域に対して延焼遮断帯として防災機能を果たすという見方もあるだろう。
しかし、火災旋風に関する一連の研究から、火災領域に面した遮風壁と広大な空地が渦巻状に熱風を引き入れ、空地側面からの側流が酸素を供給することによって、火災旋風が発達するというメカニズムが明らかにされている。木造密集地域に面する大規模再開発では、高層ビルが風速10m/秒もの上昇気流を伴う遮風壁となり、公開空地に渦巻状の熱風が引き入られ、前面の幹線道路が側流を生む、といったように意に反して火災旋風の発生条件を揃える結果にもなりうる。
ひとたび火災旋風が発生すれば、関東大震災のときの本所陸軍被服廠跡地のように、空地に避難してきた人々の命が数万人規模で失われかねない。
社会的公平性の面からみる外部不経済性
わたしたちは、公平性を尊重した社会観を共有している。同じ条件なのに差別的政策によって優遇・不遇に分かれる(水平的公平性)、大多数の犠牲のもとに少数の特権階級に富や権力が集中する(垂直的公平性)、といった事態は社会的な合意はない。東京は、本来は独裁制や階級制の都市ではなかったはずだ。
しかし一連の高層化促進政策は、結果的に、周囲の大勢の人々に犠牲を強いながら、特定の事業者に資産差益を集中させて、社会的な公平性にそむくことになっている。
①眺望の犠牲
「高層階からの眺望が魅力的」といったセールストークが良く見られるが、その背後には高層ビルの圧迫感による視覚的な不快感に悩まされる人々がいる。近年の研究によると、この圧迫感は建物の形態率(視野に占める建物外形の大きさを水平面に投影した割合)とアスペクト比(縦横比)による算定式で定まる。この算定式にモデルの数値を入れると、圧迫感を与える範囲は、タワーから295m離れた地点まで面積にして約35haに広がっている。この圧迫感によって一帯の地価は下落し、予測式(※国土交通省住宅局「景観に係る建築規制の分析手法に関する研究会:景観規制の効果の分析手法について 平成19年6月)に従えばその外部不経済の金額は24億円になる。この圧迫感による損失を、タワー側が補償したりはしない。
②しわ寄せ
立地や採算の点で優位な一部の地区については、高い容積率で事業化がされる。この事業が周辺地域のポテンシャル(住宅・消費・オフィス需要等)を吸収し、周辺の開発がそれ以上進展しない。
都心部のオフィス街の開発でも同様で、一極集中で通勤疲労費用が増える。丸の内・大手町地区で容積率を1,000%から2,000%に引き上げた場合に、この通勤疲労費用は年間430億円と試算されている。社会的割引率を4%とするとこの通勤疲労費用の現在価値は10,750億円、同地区の容積緩和による資産差益は約3兆円であるから、その1/3が通勤者の犠牲で生じる計算になる。
このように居住人口もオフィス人口も漸減する環境では、容積緩和による高層化が椅子取りゲームにしかならないのは当たり前だ。
③富めるもの、ますます富む
高層ビルを優遇する制度は、このように周りにしわ寄せが行って、特定の大地主・開発事業者を潤すことになる。モデルで確かめてみよう。
この地区はもともと容積率400%が上限で、これに対応して資産評価額も146万円/m2である。ここで様々な高層化優遇措置を受けて、実際の容積率は1,486%(=延床面積/敷地面積)にまで膨らんでいる。容積率の割増分だけ資産価値が上がるとすると、これによる資産差益は431億円に上る。従前地権者(各事業協力者)には1住戸が交換されるとして、原価ベースでみると従前地権者の得た資産差益は431億円のうちの8.0%という結果である。要するに資産差益431億円のうち、92.0%は大手開発事業者の収益源になったというのが実情のようである。
このように各種の高層化優遇制度を利用して大規模な高層ビルを事業化できるのは、実態としてごく少数の大手開発業者に限られている。こうした大手開発業者は、日影規制を撤廃して天空率規制を導入するなど、法律の改変に力を及ぼしてきた。「この設計は法律に合わないから難しいと説明すると『法律を変えてこい』…」(設計者の回想)「法律の存在自体が、何か絶対的な善を守っているような誤解を与えている。直射光は必ずしもありがたくないというケースも増えている状況下で、日影規制というのは見直すべきではないか」(某大手開発業者社長)という考え方である。
タワー公害の社会的損失額は?
高層ビル群は、東京には向かない。モンスーン気候、地震多発地帯、公平な社会といった都市環境では、高層ビルの外部不経済が著しく大きい。
モデル棟について外部不経済の金額を合計すると、輻射熱7.1億円、ゲリラ豪雨6.1億円、遮風13.2億円、スラム化34億円、圧迫感24億円と、ここまでで合計84.4億円に達する(火災旋風の被害想定分は除く)。これに、他にしわ寄せして生まれた資産差益431億円を単純に合計すると、総額515億円、一戸当たり約36百万円にも上る。これをおおまかに1,620棟分でかけると約85兆円、これ位の桁数の金額が、タワー公害による社会的損失の規模に相当する。東京直下型地震のよる被害想定は、直接被害66.6兆円、間接被害(交通寸断による機会損失・時間損失)6.2兆円、間接被害(生産額低下)39.0兆円の総計112兆円、タワー公害の社会的損失額はこれにも匹敵している。
こうした外部不経済に着目した議論に対し、「東京は土地が狭いから高層化しないと、国際的な都市間競争に負ける」といった考え方が今は主流である。しかし、先回(HOME'S PRESS記事「東京のかたち」)も触れたように、東京は、いまの容積率規制のまま、都心から10km圏に絞って中低層の街並みにしてもいまの東京の都市規模は十分に賄える。高層化しなければ、というのは単なる思い込みか、我田引水か、であろう。
約85兆円ものタワー公害を、もうこれ以上蔓延させないために、速やかに高層化促進諸制度を廃止していくべきではなかろうか?