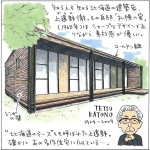訪れた誰もが感じる“幸せな裏切られ感”
本連載もゴールが近づいてきた。スタートした2年前から「明治~1970年代」を対象と考え、筆者が訪れた名住宅をほぼ竣工年順に取り上げてきた。残りあと数回だ。
今回取り上げるのは、石山修武氏(1941年生まれ)の初期の代表作である「幻庵(げんあん)」。企業経営者だった榎本基純氏(故人)が1975年に愛知県内に建てたセカンドハウスである。
実は、「“設計者の愛”の視点で名住宅を読み返す」というこの連載の試みは、幻庵を見たときの体験がヒントになっている。
筆者が幻庵を見たのは、竣工から約40年がたった2013年だ。前職の『日経アーキテクチュア』で、日建設計の山梨知彦氏が名作建築を解説する連載を担当していた。その最終回で山梨氏が「どうしても幻庵を見たい」と希望したので、石山氏に建て主を紹介してもらい、見に行った。
そのときの山梨氏の原稿の書き出しが、現地で私がモヤモヤと感じていたことをズバリ言い当てていたので、それを引用させてもらう。
「幻庵を誤解していた。いや幻庵は、誤解を生むように巧妙に仕掛けられているのかもしれない」
そうなのだ。筆者は現地を訪れるまで、この住宅を“眺めるためのアート作品”くらいに思っていた。とても人が暮らせるようなものではない、と。
その内部を体験したときの“幸せな裏切られ感”は今も忘れられない。この連載を続ける原動力と言っていいかもしれない。
暗渠に使われる「コルゲートパイプ」を構造材として使用
この家の原形になったのは、設備エンジニアの川合健二(1913~96年)の自邸(1965年)だということはよく知られている。丹下健三の「旧東京都庁舎」や「国立代々木競技場」などの設備設計も担当した川合は、土木用暗渠として使われる「コルゲートパイプ」を住宅の構造材とした自邸を愛知県豊橋市に建設。そこで自給自足の暮らしを始めた。「コルゲートハウス」とも呼ばれる川合の自邸は、見た目からして、地面に横たわる“マシン”を思わせる。
20代後半で川合と出会った石山氏が、31歳のときに完成させたのが幻庵である。
長辺方向は川合の自邸と同じようにコルゲートの板をクルッとまるめた「構造=形」のデザインだ。だが、妻面は合理性からはほど遠い。おにぎり形の妻面は下部の3分の1ほどがコンクリート。表面には波の模様が描かれている、その上は、さび止めのオレンジ色に塗られた富士山型の壁。その上はガラス。
富士山の中央にある入り口は縦長のアーチで、その左右には色ガラスがはめられた2つの丸窓。一方は上下が鉄の部材で分けられ、ウインクしているように見える。2つの丸窓の下には色ガラスをはめた丸や三角の小さな開口部がちらばる。形も色も強烈だ。
母親の胎内、あるいは宇宙に浮かぶよう
室内へ進もう。玄関は2階にある。屋外の階段でいったん2階レベルに上がり、アーチ型のドアを開けると、吹き抜けに太鼓橋が架かる。太鼓橋はメッシュ状で、下が丸見え。なので、最初は周囲を見渡す余裕がない。
その橋をおそるおそる渡り、左手の階段を下りると、ようやく緊張感から解かれる。
両側面から天井へぐるっと連続する曲面。そこにまとわりつくようにグラデーションを描く光。「まとわりつく」ように見えるのは、コルゲートのひだ(波型の凹凸)がストライプ状の影をつくり、表面のヒル石が光を反射するからだ。これが本当にあのコルゲートの板なのかと疑いたくなるほど、ぜいたくで心の鎮まる質感だ。
対して、入り口のある南面の見え方は神々しい。富士山型の壁は逆光でシルエットとなり、周囲のガラス部に見える緑がそれを強調する。色ガラスにはさまざまな光。外観ではユーモラスにも見えたが、光の強さゆえ形の印象は薄まり、“色の壁”となる。差し込んだ光は床にも鮮やかな色彩を描く。見上げると、メッシュの太鼓橋は虹のようだ。あれは下から見るためのものだったのか…。
柔らかな包まれ感と、神秘性。母親の胎内のようでもあるし、宇宙に浮かぶようでもある。
川合健二の自邸で建て主と出会う
石山氏は早稲田大学と同大学院で建築を学ぶも、就職はせず、大学院を出た1968年に設計事務所を開設した。進むべき道を模索していた石山氏は、大学の先輩に勧められて川合健二の自邸を訪ねる。衝撃を受け、その後10年間、川合の下に通った。
幻庵の建て主である榎本氏とも、川合の自邸で出会った。榎本氏もまたコルゲートパイプでつくられたこの住宅に興味を持ち、訪れていたのだ。
榎本氏は、石山氏が渥美半島に建設中だったコルゲートパイプ製の石屋のショールームを見て才能を直感した。当時、繊維問屋のオーナー社長だった榎本氏は、木々に囲まれた約1800坪の敷地を所有しており。ここに「友人を招くことができる茶席付きの建物をつくってほしい」と石山氏に依頼した。そのほかに具体的な注文はなかったという。
石山氏は要求のなさに困り果てたが、唯一の手がかりである「茶席」をキーワードに、鉄とガラスと工業製品による現代の茶室をつくりたいと榎本氏に提案した。
石山氏は、敷地の春夏秋冬を体験しながら、4~5年かけてこの建築をつくった。家具や照明はもちろん、窓や薪ストーブやスピーカーに至るまで、ほとんどがオリジナルデザインだ。パウル・クレー、曼荼羅、ウィリアム・モリス、織部、マイルス・デイビスなど、多様なイメージを掛け合わせ、ここにしかない世界観をつくり上げた。
建て主の人生を変えてしまった
石山氏によれば、建て主の榎本氏は幻庵ができた後、「小銭を稼ぐバカバカしさに気が付いたのか、植木屋さんになった」という。この家が建て主の人生観すら変えてしまったというのだ。
2006年に榎本氏は亡くなった。筆者が訪れたのは2013年で、そのときには夫人が迎えてくれた。夫人は、夫がいかにこの建物に愛着を持っていたかを語り、その例としてある場所を教えてくれた。
寝室の扉の裏面だ。そこには榎本氏が幻庵を訪れた日の日付がびっしりと書き込まれていた。石山氏の言っていたことは決して大げさではなかったようだ。
我々が訪れた際、夫人が2階の台所で昼食を用意してくれた。2階にはトイレ、浴室もある。普通に生活できる。住宅として1つの到達点にあるようにさえ思える。
アート作品のような外観も「愛」?
改めて考えるに、あのアート作品のような正面外観はなぜなのか。もっとニュートラルなデザインだったら、この住宅の内部の魅力が伝わりやすかったように思う。
筆者と共に訪問した山梨氏は、こう推測している。
「(幻庵は)まだマスプロダクションの力が信じられていた時代に、工業製品を用いて個別解を求めるという、早すぎた問答を世に仕掛けた。その早すぎる問いを自覚した設計者は、装飾的なファサードで人々の目を惑わし、いずれその本質的な問いに時代が追いつくのを待つことにしたのかもしれない」
なるほど、“つくり手”らしい見方だ。そういう考えもあったのかもしれない。しかし、もっぱら使う立場である筆者は、別の見立てをしたくなる。
「目」のように見える2つの丸窓。あれはやはりウインクなのではないか。「日輪」と「月輪」をモチーフにしたと石山氏自身は説明しているが、筆者にはどう見ても家自体が「やあ、待っていたよ」とウインクしているように見えるのである。訪れる側は「また来たよ」と声を掛けたくなる。外観から始まる家との対話。そんな楽しげな外観にしたことも、設計者がこの住宅に込めた愛なのではないか。
さらに言えば、「誤解を生むように巧妙に仕掛けた」というのも、ちょっと違うかもしれない。あれは、建て主へのストレートな愛を隠すために、「誤解を生む仕掛けに見せかけた」ものなのではないか。若き石山氏の照れとねじれ。寝室扉の写真を久しぶりに見て、そんなことを思った。
■概要データ
幻庵
所在地:愛知県
設計:DAM・DAN
施工:川崎製鉄(シリンダー製作)、大塚組(アッセンブル)、及部春雄(鉄工)
階数:地上2階
構造:ねじ式シリンダー構造
延べ面積:60.3m2
竣工:1975年(昭和50年)
■参考文献
『日経アーキテクチュア』2013年12月6日号「山梨式・名作解読/幻庵」(山梨知彦)
『TOTO通信』No500特集/忘れられた夏「幻庵」(大山直美)
『新建築.オンライン』2022年5月25日付「住宅は終わらない/石山修武(STUDIO GAYA)」(インタビュアー:家成俊勝、初出は『新建築住宅特集』2019年1月号)https://shinkenchiku.online/column/4606/