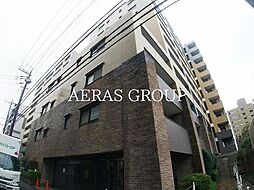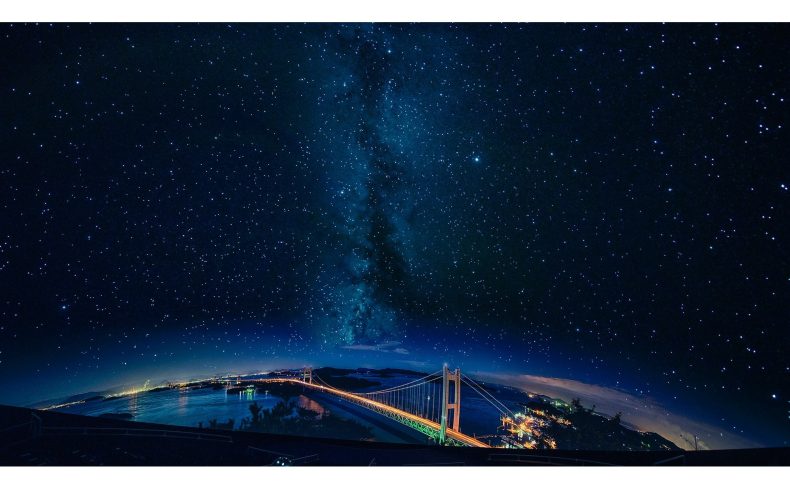茶道に興味があっても、「しきたりが多そうで不安」、「どう始めたらよいかわからない」と思う方も多いのではないのでしょうか。
私は学生時代茶道部に入っていましたが、歳月が流れすっかり茶道から遠のき、作法も忘れてしまいました。
茶道から遠のいていた時間、私のライフステージは変化し、現在は子育て中心の生活を送っています。慣れない育児でストレスを感じていたところ、何か息抜きになることはないかと調べてみると、正座をせずにテーブルに座って行う「テーブル茶道」の存在を知ったのです。
テーブル茶道を始め、その魅力に触れたことで私は心の余裕を取り戻すことができました。もちろんいまだに子育ては難しいことばかりで、気持ちが乱れることはあります。それでもテーブル茶道を始めてからは、ゆとりを持って子どもと向かいあうことができるようになりました。
そこで今回は、気軽に茶道を始めてみたい方、心にゆとりを持ちたい方に向けてテーブル茶道の魅力と始め方についてご紹介します。
テーブル茶道を始めたきっかけ

余裕のない日々の中で、思い出した茶道部の先生の言葉
里帰り出産から自宅へ帰って間もない頃、余裕がなく上手く息抜きができずにいました。泣いてばかりのわが子に対し、育児のストレスを溜め込んでしまっていたのです。
ある日、ふとテレビで茶道の映画を見て、主人公がお茶を通して自分の心や自然、そして人生と向き合いながら所作を学んでいく姿に心を打たれました。そして、私も学生時代に茶道部に入っていたことを思い出しました。
映画に描かれていたのは、学生の頃に習っていた裏千家の作法。懐かしく思い、映画の内容だけでは分からない具体的な茶道の作法を思い出すために、動画サイトで調べることに。
すると、お茶のたて方やお茶会に参加する際の作法が次々出てきます。ふくさのたたみ方を動画を見ながらやってみるうちに、おぼろげながら所作を思い出すとともに、当時茶道部の先生に言われた数々のアドバイスが脳裏に蘇ってきました。
茶道部の先生が、お稽古の初めにそわそわしている学生たちへ、かけてくださった言葉の中で忘れられないものがあります。
「ほら、掛け軸やお花を見ましょう。今日のお茶碗はどうですか? 一歩立ち止まって、周りをゆっくりと見てみて。心が落ち着くはずです。」
今の私にぴったりなのは「テーブル茶道」
茶道には、茶碗から床の間に飾られる花や花器、掛け軸などすべてに意味があります。
茶事の際に会を催すための中心となる人のことを「亭主」と言います。学生時代は主に、茶道部の先生が亭主をつとめられました。すべてに基本的なルールはあるけれど、何よりも亭主である先生が、学生が楽しく稽古できるようにひとつひとつの飾りや道具を心を込めて選んでくれたのです。
当時は深く考えず、早くお菓子を食べたいくらいにしか思えなかったのですが、今なら一歩立ち止まって客観的に自分の状況を見ることの大切さを教えてくれたのだと分かります。それは、育児で余裕のない現在の私にも響く言葉でした。
そういった心がまえも含めてあらためて茶道の魅力に気づき、茶道をもう一度習いたいと思いました。しかし、本格的な茶道は教室に長期間通わなければならず、費用面でも厳しいものがあります。家事や育児もあり、本格的な茶道の稽古をするのは難しく、なかば諦めていました。
知人に相談したところ、まずは自宅で「テーブル茶道」をやってみてはどうかと勧められました。テーブル茶道で調べてみると、茶釜でお湯を沸かす必要のない、テーブルで行える茶道であることを知ったのです。私が今育児をしながらできるのは、まさにこれだと思いました。
テーブル茶道で、赤ちゃんが寝ている合間にホッと一息
テーブル茶道に出会う前は、娘が寝るとあわてて家事をしていましたが、それをやめてお茶をたてて飲んでみることにしました。
茶道の所作を思い出しながらお茶をたてると、日々の忙しなさでささくれだつ心が落ち着いていくのを感じました。娘が昼寝をする1時間半は、テーブル茶道の作法で薄茶(※うすちゃ:少ない抹茶に多めの湯をいれたもの)をたてて飲み、片づけるのにちょうどよい時間です。
テーブル茶道で抹茶を飲んだ後は、寝起きの娘のぐずりにも落ち着いて対応できました。私の気持ちが安定していると、娘も落ち着いているようでした。
娘に余裕をもって対応することで、昼寝時間に家事を詰め込んで疲れ、部屋を汚す家族にイライラすることが減るように。以前なら夫と揉めてしまっていたことも、お茶を飲みながら相手の言いたいことがなんだったのかを冷静に考えられるようになり、以前より口げんかも減りました。自分に必要だったのはお茶を飲んでひと息つく、「自分の時間を持つこと」だったのだと気づきました。
よく聞かれるテーブル茶道のQ&A
ここからは、テーブル茶道になじみのない方に向けて、よく聞かれるテーブル茶道のQ&Aをまとめていきます。

Q:テーブル茶道と通常の茶道作法の違いは?
A:テーブル茶道と通常の茶道の一番大きな違いは、畳の上ではなくテーブルで行うことです。そのため通常の茶道で行う、客人の前で茶釜で湯を沸かすという行程はなく、あらかじめ沸かした湯を用意して行います。
Q:テーブル茶道の手順は?
私が行っているテーブル茶道の手順を紹介します。なお、たてるのは一般的によく飲まれる薄茶です。
① テーブルの上のお盆に抹茶茶碗・茶巾・茶筅(ちゃせん)・茶杓(ちゃしゃく)をのせます。茶筅はたたんだふくさで拭きます。椅子に座ります。
② 茶筅通しを行います。抹茶茶碗にポットからお湯を注ぎ、茶筅の先を抹茶茶碗の中に入れ、ゆすぎます。
③ 建水(※けんすい:お茶を入れる際に使った湯や水を捨てるための湯呑みのようなもの)に、抹茶茶碗の湯を移して茶巾で水滴を拭き取ります。
④ 花や花器、掛け軸をみてから、お菓子をいただきます。
⑤ 抹茶はお茶碗にスプーン2さじ程度入れて、ポットのお湯をお茶碗の3分の1程度注ぎます。
⑥ 茶筅でお茶をたてます。
はじめはMの字を書くよう茶筅を動かして泡立て、その後丁寧にかき混ぜるようにします。抹茶を美味しそうに見せるポイントは、抹茶の渦の中心から茶筅を抜ききる前に、“ちょん”と優しく水面に穂先で触れるこ
と。そうすると泡が真ん中に集まってふっくらとし、また抹茶の味わい自体もまろやかになります。
⑦ 抹茶をいただきます。
⑧ 片づけ
私は自分に合うように手順を簡素化してお茶をたてているので、くわしく知りたい方は調べてみてください。
Q:テーブル茶道に必要な道具は?
A:はじめは抹茶さえあれば、家にあるもので十分代用できます。
茶道の道具には、茶筅、抹茶茶碗、茶杓、ふくさ、懐紙、菓子楊枝、扇子などさまざまなものがありますが、家に茶道の道具は何もないという人はふだん使っているもので代用してみてください。
●お盆はランチョンマット
●抹茶茶碗はご飯茶碗
●茶巾はふきん、ふくさはハンカチ
●茶杓は小さめの木のスプーン
●薄茶器は抹茶が入る蓋つきの小瓶
●建水はお椀
●茶筅は小ぶりの手動泡立て器
このように、立派な道具がなくとも楽しめるものとなっています。 もちろん興味が湧いて本格的な道具をそろえたいと思うのもすてきなことです。私ははじめ、必要最低限の道具を大手通信販売サイトで4,000円弱でそろえました。
はじめはそれで満足していたのですが、しだいに道具にこだわりたくなるように。例えば茶筅の先の丸みを保ちたいと思い、茶筅のくせ直しを追加購入するまでになりました。手に入れたときと変わらずキレイな穂先を保てていることに満足しています。また、抹茶茶碗はふるさとの萩焼を取り寄せ、茶碗の模様を楽しんでいます。

Q:抹茶やお菓子はどこでそろえる?
A:抹茶も茶道でたしなむお菓子も、スーパーマーケットで手に入ります。
そもそも抹茶もお菓子も、きちんとした専門店で購入しなければならないと決まっているわけではありません。
抹茶は、スーパーマーケットで30グラム500円前後とお手頃な価格で売っているもので、十分美味しくいただけます。お菓子に関しても、私はスーパーマーケットの和菓子コーナーで自分の食べたいものを選んでいます。
なお、お菓子は自由に選んでもよいのですが、1日の分量は小皿に載る分だけと決めると、食べ過ぎずに済み、丁寧にお菓子を味わうことができるのでおすすめ。 人を招いての茶事など、特別な日は老舗の和菓子屋で購入したり、グラム単位で販売しているお茶の専門店で購入したりすると、おもてなし感が上がりますね。
Q:季節感を取り入れるとは?
A:テーブル茶道の醍醐味のひとつに、「季節を感じて取り入れる」というものがあります。できれば、二十四節気を意識するとお茶のたて方にも幅が生まれるでしょう。
二十四節気とは、一年を二十四等分し約十五日ごとの節気に分けたものです。「立春」「啓蟄」「冬至」など天候や生き物の様子で表され、季節の目安となります。
季節によって抹茶のたて方も異なるもの。また、その日の体調や、気温などに合わせてたてることも大切です。そもそものお茶のたて方も、薄茶、濃茶、暑い日はお湯ではなく冷たい水でたてる水点とさまざまなものがあります。
これらの要素を意識し、さらに何度か飲み比べることで、自分の好みの抹茶の濃さも見つかるでしょう。茶碗自体も、夏はお茶が冷めやすいよう平茶碗を用いる、寒い冬は冷めにくい筒茶碗を用いるなどのこだわりがあれば、よりいいと思います。
さらに季節感を出すのに分かりやすい要素として、お菓子選びがあります。練り切りなど和菓子の形にこだわってもよいですし、春だからぼたもちにするなど、季節を意識してお菓子を選びます。
余裕があれば、部屋に季節感を足してみてもよいかもしれません。近所の花屋で花を一本買ってきて小ビンに挿して飾ってみてもいいですね。床の間がある方は、掛け軸をかけるとより雰囲気が出ます。奥深い茶道を更に知りたいという方は、床の間の飾り方にも一定の決まりがあるので調べてみてくださいね。
私は、乳児もいるのでなかなか準備に時間をかけることができないため、インターネットで季節の行事や花を調べておいて、テーブルで抹茶を飲むときに思い浮かべています。日々のわずらわしさやタスクから一旦離れることができ、また季節の情緒を感じて癒やされています。
おうち時間が充実、テーブル茶道の魅力

足がしびれない、テーブル茶道
テーブル茶道のよいところは、椅子に座って行うため足がしびれない点です。
学生時代、茶道部での活動していたときは足のしびれとのたたかいでした。足がしびれにくい正座のコツや、しびれても跪座(きざ)の体勢というしびれ逃しの姿勢もありますが、慣れるまではなかなか大変です。
少しずつ慣れるとはいえ、ベテランの講師の先生でもしびれることはあります。やはり、しびれないに越したことはありません。
また、私は子どもと一緒にいる時間が長く、掃除のしやすいフローリングの部屋で過ごすことが多いです。フローリングの部屋でもできるテーブル茶道は、子どもと一緒にいながら抹茶を味わえるので、そういった面でも自分に合っていると感じます。もう少し子どもが成長したら、子どものおやつ時間に一緒に抹茶を味わいたいですね。
庭の草木に四季のうつろいを感じて
庭のある住まいであれば、庭の景色が見える位置に座ると季節を感じやすくなります。ガラス越し、あるいは少し窓を開けて外の景色を眺めましょう。
私の家は、ベランダ越しに桜の木が見えるので、春に満開の桜を見ると明るい気持ちになります。桜の花や葉や枝そのものを見るだけでも、春夏秋冬を感じます。家にいながら季節を感じられると、抹茶やお菓子もより美味しくなりますよ。
ベランダやバルコニー、お庭がある住まいであれば、より季節の空気を感じられテーブル茶道の楽しみを増やすことができます。
テーブル茶道教室に通うのにおすすめなエリア
テーブル茶道をきちんと習得したいと思った方は、テーブル茶道の教室に通ってみるのもよいかもしれません。
教室によって料金設定が異なります。例えば講師を目指すコースだと全日程で20万円前後かかりますが、1dayレッスンなどであれば1回3,500円程度で受講できるところもあります。
私は関東で暮らしており、家から通える範囲のテーブル茶道の教室に通っています。テーブル茶道の教室は各地にありますが、関東では横浜市に多い印象です。
その中のひとつ、横浜市青葉区は独身時代に私が住んでいたエリアでもあります。女性の一人暮らしでも安心して暮らすことができ、治安がよいと感じた地域です。
東名高速道路の横浜青葉ICがあることや、渋谷まで電車で30分圏内であり、都心へのアクセスも良好。名前のとおり緑の多い青葉区は、季節を感じるのに最適な住みやすい場所です。青葉区は結婚を機に離れましたが、今でもふらっとお茶をしに行きたくなります。
ぜひテーブル茶道に興味を持っている方は住まいの近くの教室を探してみてくださいね。
神奈川県横浜市の賃貸物件
いつものおやつ時間にテーブル茶道を楽しもう
テーブル茶道は、自宅で気軽に始めることができます。まずは、いつものおやつ時間に抹茶をたてて、季節感のあるお菓子を味わってみることから始めてみてはいかがでしょうか。
そして抹茶を飲むときは、日々の喧騒を忘れ、一度周りをゆっくりと眺めてみてください。余裕のない日々だからこそ、やらなければならないことから一旦離れ、ひと息つくことで見えてくるものもあります。自分なりの方法で、テーブル茶道を取り入れてみてくださいね。