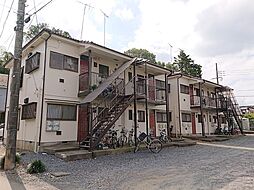私は沖縄が大好きで、約4年前に移住してきました。
移住してきて驚いたことの一つに、沖縄に到達したときの台風の大きさがあります。聞けば、沖縄県民は「hPa(ヘクトパスカル)数を聞けば、台風の規模感がイメージできる」とか、「台風の勢力は本土にいくにつれて弱くなるはずなのになぜ大きな被害が出るのか不思議だ」というではありませんか。
そう語るだけあり、沖縄県民は大型の台風に慣れています。長年の知恵と経験によって台風への対策も詳しく、勢力の強い台風が来た際、土砂災害や暴風によって大木が根こそぎ倒されるといった自然災害こそあるものの、対策不足による大きな被害が出ることはあまりないといいます。また、停電などが起こったときの乗り切り方が上手だと感じます。
今回は、そんな沖縄の大きな台風を何度か経験した私が、沖縄県民から伝授された内容を基に、大きな台風への備え方のポイントをお伝えします。
- 大型台風が年に数回接近する沖縄の台風対策から学べること
- 沖縄に住むわが家の台風事情
- 勢力の強い台風を毎年経験している沖縄県民の台風対策
- 台風対策の基本
- 台風発生から接近までに考えておくべきこと
- 台風対策に日頃から準備しておきたいもの
- 台風被害が大きくなった際の避難場所などを家族で話し合っておく
- 台風直前に行う対策
- 家の中の台風対策
- 家の外の台風対策
- 停電への備え
- 台風通過時・通過後の対策
- 台風で停電してしまった場合の対処法
- 台風で窓が割れてしまった場合の対処法
- 台風の通過後にできること
- 大きな台風にも備えやすい物件のポイント
- 雨戸付きの物件
- 鉄筋コンクリート造の住宅を選ぶ
- 豪雨となっても大丈夫な立地の物件を選ぶ
- 家の台風対策は、あらゆる被害を想定した事前準備が大事
大型台風が年に数回接近する沖縄の台風対策から学べること

年間の台風接近回数が関東地方へは約3回程度であるのに比べ、沖縄へはなんと年間約8回。ここ数年では、2018年の台風21号が大きな被害をもたらしました。それだけ台風が接近する頻度が高い沖縄の台風対策への危機感は、私が福岡に住んでいたときとは桁違いに大きいものでした。
まずは、沖縄で行われている強い台風への対策意識をご紹介します。普段の台風対策はもちろん、大きな台風が来るとなった際に役に立つ内容ですので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
沖縄に住むわが家の台風事情
私は現在、高台にあるマンションの5階に住んでいます。台風時には強風で建物の揺れを感じますが、高台という場所のおかげで安心感はあります。
最初に沖縄に引越してきて家を選んだときは、台風の大きさやその被害がどの程度のものになるのか見当がつきませんでした。生活していく中で次第に被害の程度が分かったので、“事前に予想できる自然災害はなるべく避けた場所に住みたい”という考えで今の家を選びました。
勢力の強い台風を毎年経験している沖縄県民の台風対策
台風発生から間もないタイミングで接近・上陸することが多い沖縄。まず驚いたことは、台風が近づくとスーパーやコンビニから、パンやカップラーメンなどの日持ちのする食料がすぐなくなるということです。台風の勢力が強くなれば強くなるほど商品がなくなるので、それを見て「今回の台風の強さがどれほどのものなのか」というのを測る目安になるのです。
また、私が福岡に住んでいたときに体験したことがなかったのが、「台風で物が飛ぶ」ということ。勢力の強い暴風によって、ベランダや庭の鉢植えやスリッパなどが簡単に飛びます。自分の家のものであれば事前に室内に入れますし、どこかから何かが飛んできて窓ガラスが割れたとしてもその被害が最小限で済むように、窓ガラスにはバッテン(×)にガムテープを貼ります。
台風対策の基本

台風対策の基本は、とにかく被害が大きくならないようにすること、台風通過中でもなるべく快適に過ごせるような状態を作っておくこと、勢力が大きいと予測されるときは避難も視野に入れておくこと、そして事前に準備をすることです。
私もそうですが、普段はあまり考えることのない方も、勢力が強い台風が接近・上陸する前には必要な準備を終わらせるようにしておきましょう。
台風発生から接近までに考えておくべきこと
台風が接近するまでに考えておきたい大まかなことは、家の外で起こりうる被害のこと、停電になったときのこと、水が使えなくなったときのこと、避難しないといけなくなったときのことの4つが挙げられます。
この4つの観点から準備をすると、大きな台風でも乗り切ることができます。
台風対策に日頃から準備しておきたいもの
台風の直前に全てを準備しようとすると大変ですよね。日頃から準備しておくと、普段はもちろん、いざというときにも役に立つものもあります。
例えば、生理用品やコンタクト液などの生活用品など、普段使っていてないと困るというものは、ストックを切らさないようにしておくと安心。
他にも、カセットコンロ用の替えのガスボンベなどはIHクッキングヒーターの家では万が一停電してしまった際に使えます。冬の時期に使うことが多いかもしれませんが、夏場でもストックを切らさないようにしておくと、停電した場合などに役に立ちます。
また、地震への備えに使える防災グッズも、台風接近の機会を利用して内容を見直しておきましょう。地震だといつ来るか分からないので防災への意識が希薄になりがちですが、台風などのように予測できる災害はその限りではありません。防災グッズの中身や、非常食・水の使用期限などを確認しておくことで、台風での避難が必要になった際はもちろん、それ以外の災害時にも役に立つでしょう。
台風被害が大きくなった際の避難場所などを家族で話し合っておく
お住まいの市町村などで、「地域で起こりうる災害情報」をまとめたハザードマップが作られています。自分が住んでいる地域ではどのような災害が起こりうるのか、避難場所はどこなのかなど、一度確認しておくことをおすすめします。
被害が大きくなって避難が必要になった際、どのように行動するかということを家族で話し合っておくといいでしょう。事前に話し合っておけば、実際に災害がひどくなって携帯電話での連絡が取れなくなっても、どこに避難しているかの目処がつきますね。
台風直前に行う対策

沖縄では、台風が近づくとスーパーから物がなくなります。特に大型の台風が接近する際は、全てのパンやカップラーメンなどが陳列棚から消え去る、といっても過言ではないほど。
これは、台風が去った後も海が荒れている影響で、物流が止まる可能性を考慮しているため。台風の渦中だけでなく、その後2~3日分の生活必需品を備えているのです。
家の中の台風対策
家の中の台風対策は主に2つあります。
1つ目は、室内の通気口をふさぐというものです。台風の暴風雨によって、通気口から水が入ってくることもあるので、あらかじめふさいでおくと安心です。
2つ目はすでにご紹介したとおり、窓ガラスに内側からガムテープかダンボールをバッテン(×)の形で貼っておくこと。物が飛んできて窓ガラスに当たったとしても、破片が飛び散るのを最小限に防ぐことができます。
家の外の台風対策
次に、家の外の台風対策についてご紹介します。
まずは、物干竿やサンダル、植木鉢といったベランダの物を家の中に入れます。強風で飛ばされた際に、物がなくなってしまうだけでなく、自分の家から飛んだものが近隣の家へ被害をもたらしてしまう危険もあるためです。台風時は雨の被害もあるので、排水溝のつまりをあらかじめ取り除き、二次災害を防ぎましょう。
屋外に洗濯機を置いている場合は、水をいっぱい溜めておき、風で動いたり飛ばされたりしないようにしておくのも重要です。普段ペットを外で飼っている場合も、家の中へ避難させてあげましょう。
停電への備え
台風で起こりうる災害の一つに、停電があります。電気が使えないと日常生活自体送るのが不便になりますし、台風は暑い時期にやってくるので、クーラーが使えないとなると快適さが失われますよね。ここでは停電への備えをご紹介します。
冷蔵庫の停電対策
まずは、500mlのペットボトルを4本ほど凍らせておきます。停電で冷蔵庫の電源が落ちてしまった際、凍ったペットボトルを冷蔵室へ移すことで、温度が下がっていくのを緩やかにすることが可能に。冷蔵庫の中の食品の鮮度を保つことができます。
ポイントは、2Lなどの大きなペットボトルではなく500mlのものを使用すること。食材の隙間に入れるなど、小分けにして使うことができ便利です。
水を確保しておく
浴槽に水を溜めておくのも有名な対策ですよね。停電になると、水道が使えなくなったり、トイレの水が流せなくなったりする可能性があります。
浴槽の水を桶に汲んで流すことでトイレの水も流せるようになります。その他、手を洗うなどさまざまな場面で利用することができます。
車のガソリンを満タンにしておく
夏場に停電した際、クーラーが使えなくなるととても困りますよね。車のガソリンを満タンにしておけば、冷房の効いた車内で過ごすことができます。また、家からどこかに移動しなくてはならないときにも、ガソリンが満タンになっていれば安心して移動することができます。
現金を用意しておく
時代はキャッシュレス化が進んでいますが、やはり現金が必要な場面もあります。特に停電時は、キャッシュレス機器が使えないという場合も。台風前に口座から現金をおろしておくようにしましょう。
台風通過時・通過後の対策

事前準備が間に合わなかったり、準備していたにもかかわらず何かしらの被害を受けたりした場合、台風通過時・通過後の対策が必要になります。
台風で停電してしまった場合の対処法
停電に備える対策は先に紹介しましたが、もし事前に対策することなく停電してしまった場合は、そのときにできることをするしかありません。
停電になったらすぐにお風呂に水を溜めておきましょう。これは、いつ水が使えなくなるか分からないので、できるうちに対策をしておくものです。
電気がいつ戻るのか目処がつかないうちは、冷蔵庫の開け閉めをする回数を控えるなどして、冷蔵庫の中のものを腐らせないようにします。
外が明るいうちの停電であれば、暗くなる前に避難所に移動しておくか、いつでも避難できるように防災グッズを玄関に準備をしておくといった行動も求められます。
台風で窓が割れてしまった場合の対処法
窓が割れてしまった場合は、まず破片で怪我をしないように片付けをします。ゴミを捨てる際には市町村のゴミ捨てルールに沿って処分しますが、その際に他人が怪我をしてしまわないよう、「ガラス・危険」など赤字で記載するなどして配慮しましょう。
割れた窓ガラスは修理をする必要がありますので、賃貸の場合はまず不動産管理会社に電話を入れて相談してみましょう。また、保険でまかなえる場合もあるので、保険会社にも相談します。
修理会社の人が来るまでは、ビニール袋や段ボール、木の板などを使って割れた部分を保護しておきます。
台風の通過後にできること
台風が過ぎ去ったら、できる限り元の状態に戻しましょう。外は、木の葉やどこからか飛んできたものなどで散らかっている可能性があります。それらが流れて排水溝が詰まってしまったり、怪我する人が出たりといった二次被害が出ないよう、迅速に片付けましょう。
大きな台風にも備えやすい物件のポイント

普段は何も気にすることなく住んでいても、大きな台風が来るとなったら急に心配になりますよね。しかし、住み始めたあとに物件に対してできる台風への準備は限られているもの。物件を選ぶ際にも台風のことを少し意識すると、心の余裕ができるかもしれません。
雨戸付きの物件
マンションやアパートだと、雨戸付きの物件はそう多くないかもしれませんが、一戸建てだと雨戸付きの物件を選ぶのもいいでしょう。
雨戸は雨風を防ぐだけでなく、台風時などの風が強いときに物が飛んできてもその被害を抑えられるといった安全性を担保してくれます。雨風・台風の対策以外にも、防犯や家の中への断熱など、さまざまな効果が期待できます。
鉄筋コンクリート造の住宅を選ぶ
住宅の構造を意識するのも、台風時に安心して過ごせる家選びのポイントの一つ。
鉄筋コンクリート造の住宅は、他の構造に比べて耐風性や耐候性が高く、被害を最小限に抑えることにつながります。
台風による大きな破損がなければ、修繕費用も抑えられるでしょう。
豪雨となっても大丈夫な立地の物件を選ぶ
数年前に九州豪雨が発生したとき、山あいの川のすぐ横に立っていた私の親戚の家は大きな被害を受けました。家の土台となる部分が、河川の上流から流れてくるものすごい勢いの濁流に削られてしまったのです。先代が建てた家で商店も営んでいましたが、危険な状態となり、今はもう住めなくなってしまいました。
普段は何気なく親しんでいる水ですが、その量が多くなると、猛威をふるいます。台風の影響で雨量が増えると河川への影響が出ることもあるので、なるべくなら河川近くの物件を避けて選ぶというのも台風時に安心して過ごせる物件選びのポイントとなるでしょう。その他、崖崩れなどが起こりそうな場所も避けたいですね。
家の台風対策は、あらゆる被害を想定した事前準備が大事
本土の台風の被害が大きくなるのは数年に一度程度なので、普段はそこまで意識しないですよね。しかし、実際に台風が接近すると、暴風雨は強さを増す一方で、外出するのも危険な状態になるので、台風がくると分かったら、普段よりも用心して対策をしましょう。
多くの台風を経験してきた沖縄で培われた対策と意識。今回ご紹介した内容が、皆さんの身の安全につながれば幸いです。